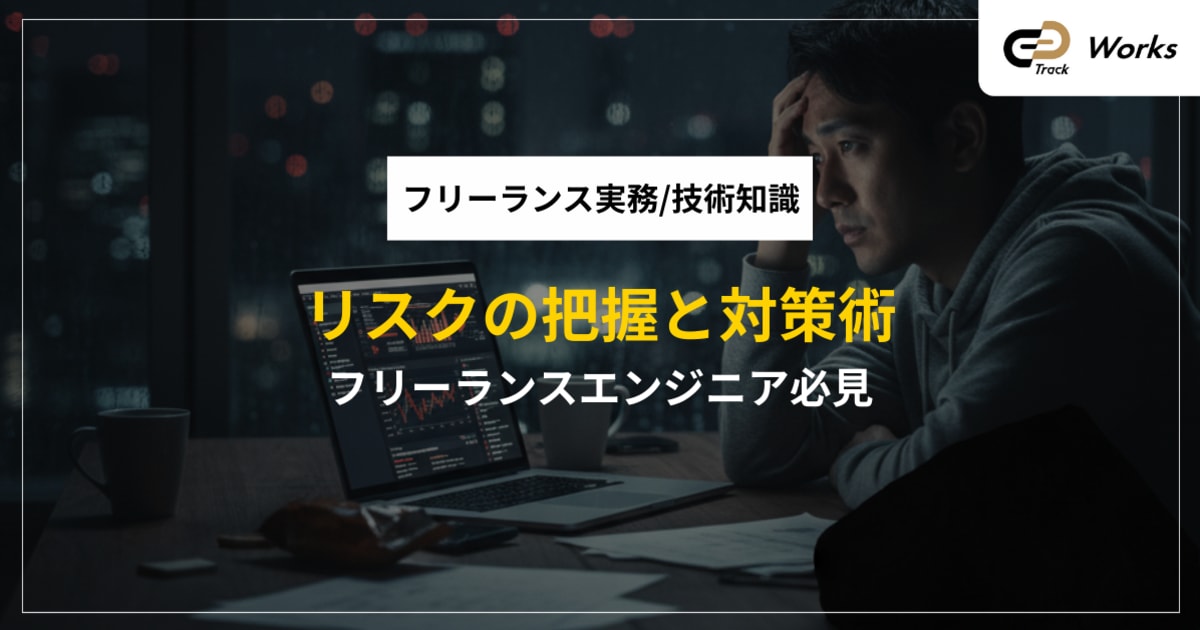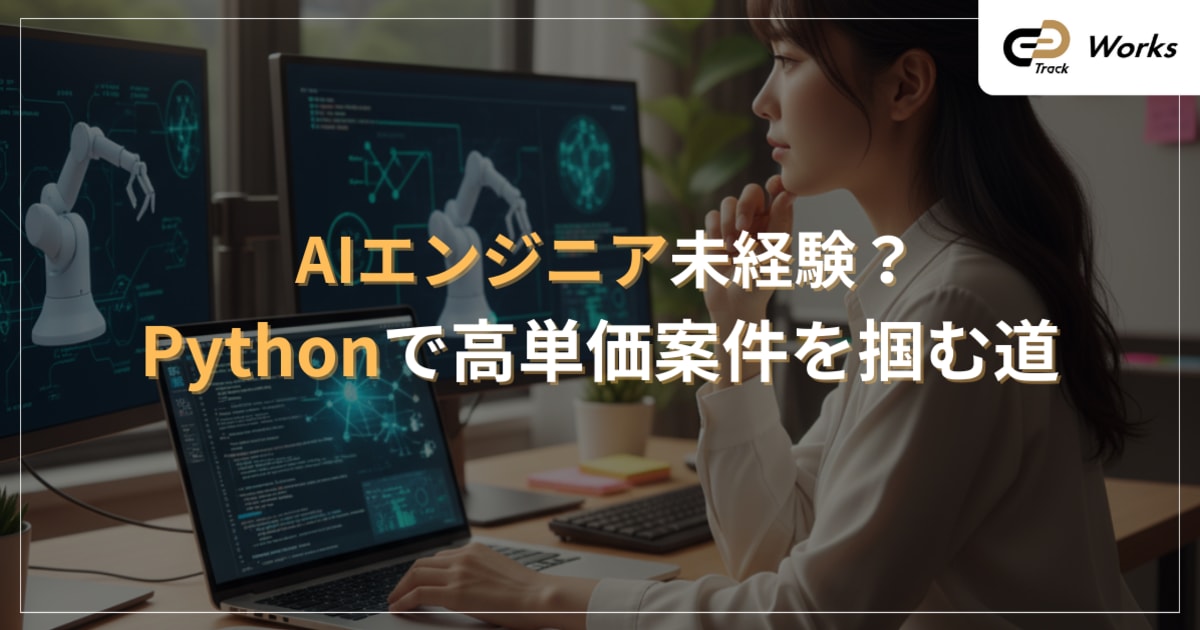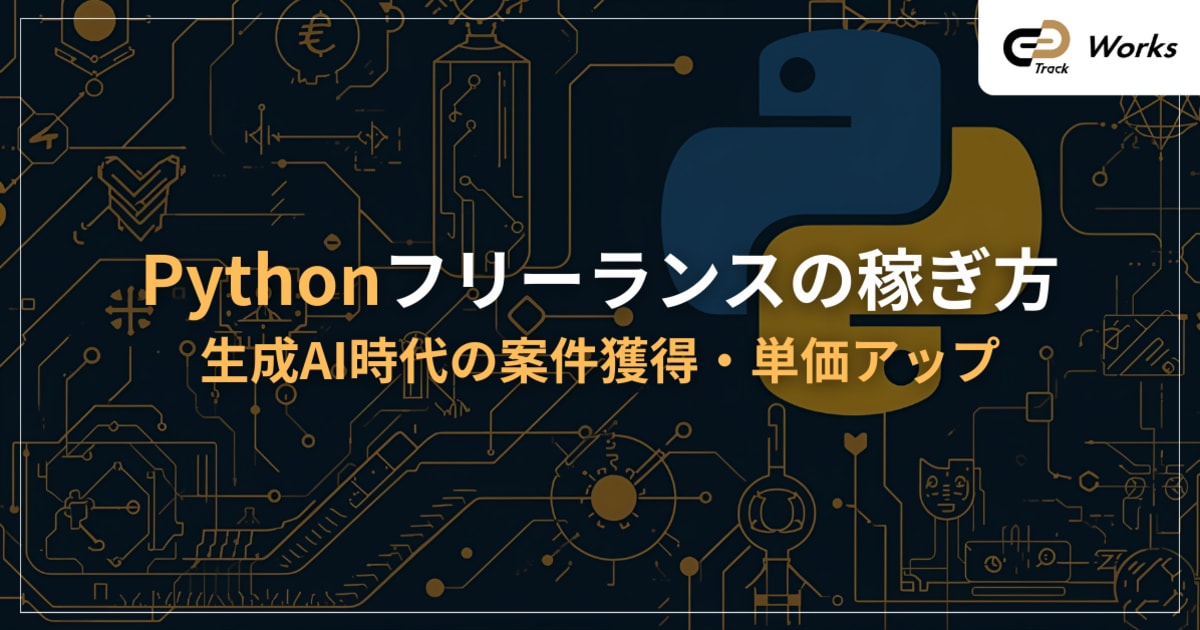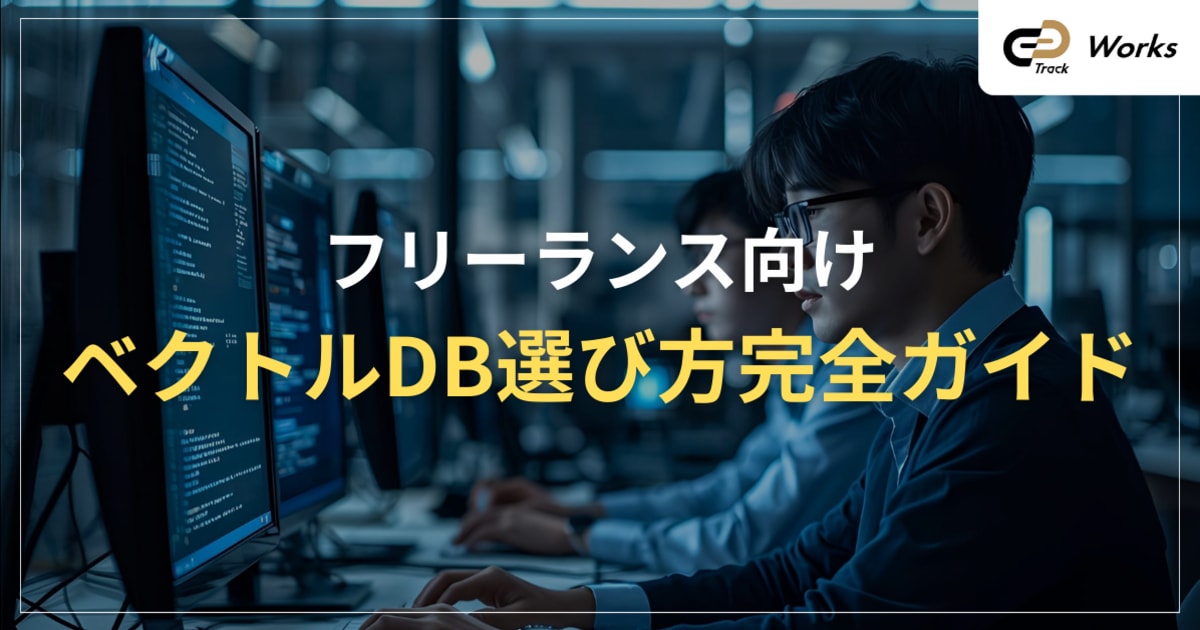本記事では、フリーランス契約書テンプレートを使いこなすための基本と注意点を、エンジニア目線で整理し、案件トラブルを避ける実践的なポイントをまとめます。 フリーランスエンジニアとしての一歩を踏み出す方や、フリーランス転向・副業を検討しているエンジニアの皆さんが、希望に満ちたキャリアのスタートでつまずかないために、絶対に知っておくべきなのが「契約書」の知識です。
「クライアントは良い人そうだから大丈夫」「細かい話は後で…」そんな油断が、後々の大きなトラブルに繋がりかねません。契約書は、あなた自身のスキル、時間、そしてキャリアを守るための重要な防御手段です。
具体的には、なぜ契約書が必要なのかという根本的な理由から、チェックすべき項目、契約書テンプレートの賢い使い方、そして本当に困ったときの相談先まで、公的機関の情報を中心に、信頼できる情報源を参照しながら、初めての方にも理解しやすい形で解説します。
フリーランスエンジニアとして独立するうえでは、契約書の知識だけでなく、収入の波や案件獲得、税金・社会保険、スキルの陳腐化、健康面など、働き方全体のリスクもあらかじめ押さえておくことが重要です。こうしたフリーランスのリスク全体像と具体的な対策については、以下のコラムで詳しく解説しています。
※本記事は、中小企業庁や公正取引委員会のガイドライン、フリーランス保護新法等の公的情報を参照し、一般的な法解釈に基づいて作成されています。しかし、個別の事案に対する法的な助言や有効性を保証するものではありません。具体的な契約に関する判断や契約条項の解釈、交渉戦略については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。特に高額案件や複雑な契約内容の場合は、事前の専門家によるリーガルチェックを強く推奨いたします。
1. なぜフリーランスに契約書が必要なの?
フリーランスの働き方は、会社員と異なり労働基準法の直接的な適用対象外ですが、2024年11月1日に施行された『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律』(通称:フリーランス保護新法)により、発注者に対して取引条件の明示義務や報酬支払期日の遵守義務が課されるなど、フリーランスの取引環境改善が図られました。 それでも、個別の取引条件を明確にし、クライアントと対等な関係を築く上で、自分自身で仕事のルールを定める「契約書」が依然として不可欠です。これは、お互いが気持ちよく仕事を進めるための「共通のルールブック」であり、信頼関係の証でもあります。
1.1 フリーランスが口約束やチャットだけで済ませて契約書を作らないのが危険な理由
日本の民法上、契約は当事者双方の意思が合致すれば口頭でも成立します(諾成契約)。しかし、口約束は記憶が曖昧になりがちで、「言った」「言わない」の争いになった際に、合意内容を証明する客観的な証拠がありません。
また、SlackやChatworkなどのビジネスチャットでの合意も注意が必要です。日々の膨大なやり取りの中に重要な合意事項が埋もれてしまい、いざという時に探し出すのは非常に困難です。正式な書面がなければ、「そんな依頼はしていない」「金額が違う」といった水掛け論になり、弱い立場であるフリーランスが泣き寝入りするケースは後を絶ちません。
1.2 フリーランス契約書が果たす「期待値調整」と「信頼の土台」としての役割
契約書は、単にトラブルを防ぐためだけの守りのツールではありません。プロジェクト開始前に、クライアントとフリーランス双方の「期待値」をすり合わせるための、極めて重要なコミュニケーションツールです。
- 業務のゴールは何か?(What)
- 誰が責任を持つのか?(Who)
- いつまでにやるのか?(When)
- どこまでやるのか?(Where)
- なぜこの業務が必要か?(Why)
- どうやって進めるのか?(How)
これらを文書で明確にすることで、「こんなはずじゃなかった」という不幸なすれ違いを防ぎます。明確な契約書を交わすことは、クライアントに対して「私はプロとして責任を持って仕事に取り組みます」という意思表示にもなり、信頼関係の強固な土台となります。
1.3 フリーランス契約書がない場合に起こりやすい典型的なトラブル事例
契約書を交わさない、あるいは内容が曖昧な場合に起こりがちなトラブルは、フリーランス協会が発行する「フリーランス白書」でも数多く報告されています。
- 納品後に終わりのない修正要求が続くケース: 「軽微な修正」という言葉を盾に、納品後数ヶ月間際限なく修正を要求される。
- 大幅な仕様変更による無償労働: 開発終盤になって「やっぱり方向性が違うから、最初から作り直して」と、スコープ外の作業を無償で求められる。
- 報酬の支払い遅延・減額: 「思ったより売上が上がらなかったから」という理由で、一方的に報酬を減額されたり、支払いが数ヶ月遅れたりする。
- 成果物を無断で商用利用されるケース: 納品したソースコードを、クライアントが自社プロダクトとして勝手にパッケージ販売し、大きな利益を上げていた。
これらのトラブルは、誰にでも起こり得るものです。
【参考資料】 公正取引委員会: フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン フリーランスとの取引で問題となる行為や、発注事業者が講ずべき措置が具体的に解説されています。 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/freelance_gl.html e-Gov法令検索: 民法 第五百二十二条(契約の成立と方式) 契約が書面の作成を要せず、口頭でも成立する根拠条文です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 フリーランス協会: フリーランス白書 フリーランスが実際に経験したトラブルに関する統計データが掲載されています。 https://www.freelance-jp.org/whitepaper
出典・引用:1 https://mid-works.com/columns/freelance-career/freelance-selfemployed/11414814 https://note.com/kokoro_rosca/n/n3cf79ecf0a7a
2. フリーランス契約書の基本構成と必須項目
**2024年11月1日に施行された「フリーランス保護新法」**により、発注者側はフリーランスに業務を委託する際、以下の項目等を書面やメール等で明示することが義務付けられました。これらは契約書の必須項目と捉え、必ず確認しましょう。
2.1 フリーランス契約書の当事者の情報(誰と誰の契約か)
契約の責任の所在を明確にするための基本情報です。
- 個人事業主の場合: 氏名、住所、屋号(あれば)
- 法人の場合: 法人名、本店所在地、代表者名 記載された情報が不正確だと、契約の有効性や履行に支障が出る可能性があります。必ず正確に記載しましょう。
2.2 フリーランス契約書における業務内容・納品物の範囲(何をどこまでやるか)
契約の心臓部です。曖昧さを徹底的に排除し、誰が読んでも同じ解釈ができるように具体的に記述することが重要です。
- 業務内容: 「ECサイトのフロントエンド開発」だけでなく、「React/Next.jsを用いた商品一覧ページ、商品詳細ページ、カート機能の実装」のように、使用技術や担当範囲を明記します。
- 納品物: 「ソースコード一式」だけでなく、「GitHubリポジトリへのプッシュ」「テスト仕様書」「基本設計書」など、納品する対象物をリストアップします。
- 仕様変更のルール: 「仕様変更が生じた場合は、別途協議の上、追加の費用と納期を定める」といった一文を入れておくと、無償での追加要求を防ぐ防波堤になります。
2.3 フリーランス契約書における報酬・支払い条件(お金の話は最重要)
報酬額はもちろん、支払いプロセス全体を明確にします。
- 報酬額:
金1,100,000円(消費税100,000円を含む)のように、税抜・税込金額を明記します。 - 支払条件: 「検収完了月の翌月末日までに、指定の銀行口座に振り込む」など、支払日を確定させます。
- 検収プロセス: 納品後、何営業日以内にクライアントが内容を確認(検収)し、合否を通知するのかを定めます。検収期間が不当に長いと、その分支払いが遅れる原因になります。
- 諸経費の負担: 交通費やサーバー代などの経費が発生する場合、どちらが負担するのかも明記しておきましょう。
2.4 フリーランス契約書の契約期間・更新条件(いつからいつまで、どう続けるか)
業務の期間を定めます。
- 期間の定め:
2025年10月1日から2026年3月31日までのように、開始日と終了日を明記します。 - 自動更新条項: 月額報酬の顧問契約などでよく使われます。「期間満了の1ヶ月前までにいずれか一方から書面による申し出がない限り、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする」といった条項です。意図しない契約延長を防ぐためにも、更新のルールは必ず確認しましょう。
【参考資料】 公正取引委員会: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)の概要 発注者がフリーランスに明示すべき事項が具体的に定められています。 https://www.jftc.go.jp/freelance/index.html
出典・引用:1 https://japan-design.jp/freelance/9128/2 https://tng-marketing.com/freelance/knowledge/contract/3 https://goworkship.com/magazine/outsourcing-note/5 https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/
3. フリーランスがよく使う契約書の種類
フリーランスエンジニアが関わる契約は、主に「業務委託契約」ですが、その性質によって2つのタイプに分かれます。この違いを理解することは、自分の責任範囲を正しく認識する上で非常に重要です。
3.1 フリーランス契約書でよく使う業務委託契約(準委任契約・請負契約)
- 準委任契約(民法第656条、第643条以下):
- 目的: 業務の遂行そのもの(労働力や専門的知見の提供)。
- 責任: 善良な管理者の注意をもって業務を行う義務(善管注意義務)。つまり、「プロとして、誠実に、やるべきことをやる」責任を負いますが、必ずしも成果物の完成までは保証しません。
- 例: SES契約での客先常駐、技術顧問、アジャイル開発チームへの参加など、時間単位や人月単位で稼働する場合。
- 請負契約(民法第632条以下):
- 目的: 仕事の完成(成果物の納品)。
- 責任: 成果物を完成させて納品する責任。納品物にバグや仕様通りの動作をしないなどの欠陥(契約不適合)があった場合、修正や代替物の納品、場合によっては損害賠償の責任を負います(契約不適合責任)。
- 例: Webサイト制作、スマホアプリ開発、特定の機能開発など、明確な「完成品」がある場合。
自分の案件がどちらの性質に近いか、契約書の内容が実態と合っているかを確認しましょう。「準委任」のつもりで働いていたのに、契約書が「請負」になっていると、予期せぬ完成責任を問われる可能性があります。契約の性質や責任範囲について不明な点がある場合は、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
3.2 フリーランス契約書とセットで結ぶことが多いNDA(秘密保持契約)
NDA(Non-Disclosure Agreement)は、業務上知り得たクライアントの非公開情報を外部に漏らさないことを約束する契約です。
- 確認ポイント:
- 秘密情報の範囲: 何が秘密情報にあたるのか(顧客データ、開発中の技術、経営情報など)が具体的に定義されているか。
- 秘密保持義務の期間: 契約終了後、いつまで秘密を守る義務があるのか(例: 契約終了後3年間)。永久に義務を負うような内容は交渉の余地があります。
- 返却・破棄義務: 契約終了時に、預かった情報や資料をどうするのか(返却するのか、破棄するのか)が定められているか。
3.3 副業・兼業フリーランスに関する契約書
会社員が副業をする場合、まず本業の就業規則を確認することが絶対条件です。その上で、副業先と契約を結ぶ際は、本業の業務に支障をきたさないこと、そして本業の会社の情報を漏洩しないことを明確にする必要があります。特に、本業と同じ業界の企業と契約する際は、競合する業務を行わないことを約束する「競業避止義務」に注意が必要です。
【参考資料】 e-Gov法令検索: 民法 請負(第六款)、委任(第九款)の条文を確認できます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 経済産業省: 秘密情報の保護ハンドブック NDAの考え方や条項例が詳しく解説されています。 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook.pdf
出典・引用:3 https://tech.hipro-job.jp/column/7904 https://topics.type.jp/type-engineer/engineer-job-market-trend/-subcontracting/
4. フリーランス契約書のテンプレートを活用するメリットと注意点
今やネットで手軽に契約書のテンプレートが入手できます。これらを賢く利用し、リスクを避けるためのポイントを解説します。
4.1 フリーランス契約書のテンプレートを使うメリット
最大のメリットは、「たたき台」が手に入ることによる時間と手間の削減です。契約書に必要な基本的な条項(当事者情報、目的、契約期間、解除条項、管轄裁判所など)が網羅されているため、ゼロから作成する労力を省き、法的に重要な項目の抜け漏れを防ぐことができます。
4.2 フリーランス契約書のテンプレートをそのまま使う最大のリスク
テンプレートはあくまで汎用品であり、案件ごとの実態に完全に適合することはありません。そのまま利用すると、業務内容や責任範囲に齟齬が生じるリスクがあります。
- 業務実態との乖離: テンプレートの業務内容が曖昧なため、後から「これも契約の範囲だ」と追加作業を要求される。
- 不利な条項の見落とし: テンプレートに、発注者側に有利な条項(例: 知的財産権の全面譲渡、損害賠償の上限なし)が紛れ込んでいることに気づかずサインしてしまう。
- 法改正への未対応: 古いテンプレートを使い、フリーランス保護新法などの新しい法律に対応していない内容で契約してしまう。
4.3 フリーランス契約書のテンプレートを自分の案件に合わせてカスタマイズすべきポイント
テンプレートは「下書き」と割り切り、自分の案件に合わせてカスタマイズする意識が重要です。
- 業務内容の具体化: テンプレートの「第〇条(業務内容)」を、あなたのプロジェクトに合わせて、使用言語、担当フェーズ、機能一覧などを追記・修正する。
- 知的財産権の調整: 「成果物の著作権は乙(受注者)に帰属する。ただし、甲(発注者)は本契約の目的の範囲内で自由に利用できるものとする」といったライセンス形式の条項や、「乙は、自身のポートフォリオとして本件成果物を公開できるものとする」といった一文を追加する交渉を検討してみましょう。
- 損害賠償の上限設定: 実務上は、「甲乙の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、その賠償額は、本件業務の委託料の総額を上限とする」という条項を設けるケースもあります。ただし、案件の性質や業界慣行によって異なり、必ずしも認められるわけではないため、交渉を検討しましょう。これは法律で定められた権利ではなく、契約交渉によって勝ち取るべき重要なリスク管理手法です。
これらの条項の修正や交渉については、個別の事情により適切な内容が大きく異なります。特に重要な条項の変更を検討する際は、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
【参考資料】 中小企業庁: 取引適正化に向けた自己診断チェックリスト 契約内容が自社にとって不利でないかを確認する際の参考になります。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2021/211224checklist.pdf
出典・引用:2 https://freeconsultant.jp/column/c223-2/5 https://biz.moneyforward.com/contract/basic/9279/
5. フリーランス契約書で特に注意すべき「3大キラー条項」
契約書の中でも、フリーランスの権利や将来のキャリアに致命的な影響を与えかねない条項があります。以下の3点は、特に注意深く確認してください。これらの条項に関する判断は、必ず弁護士等の専門家にご相談いただくことを強く推奨します。
5.1 フリーランス契約書における知的財産権の帰属
あなたが寝る間も惜しんで書いたソースコードや、生み出したデザインの権利(著作権)がどうなるかを定める条項です。
- フリーランスにとって非常に不利になり得る条項:
本件業務により生じた成果物に関する一切の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、成果物の引渡しをもって、乙から甲に無償で移転する。 - 何が問題か: これに同意すると、あなたはその成果物を自分の作品としてポートフォリオに載せることも、そこで得た知見を活かして類似のコードを別の案件で書くこともできなくなる可能性があります。あなたはただの「作業者」となり、生み出した価値はすべてクライアントのものになります。
- 対策の例: 前述の通り、ポートフォリオへの掲載許可や、権利の利用許諾(ライセンス)形式への変更を交渉しましょう。また、「著作者人格権は行使しない」という条項もセットで入っていることが多いですが、これは「『このコードは私が作った』と公表したり、意に反する改変を止めたりする権利を使いません」という意味です。この権利は譲渡できないため、このような表現が使われます。具体的な交渉内容や条項の解釈については、弁護士等の専門家にご相談ください。
5.2 フリーランス契約書における損害賠償責任の範囲
あなたのミスでクライアントに損害を与えた場合の賠償責任を定める条項です。
- フリーランスにとって非常に不利になり得る条項:
乙の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、乙はその一切の損害を賠償する責任を負う。 - 何が問題か: 「一切の損害」には上限がありません。例えば、あなたのバグが原因でクライアントのECサイトが半日停止し、数千万円の機会損失が発生した場合、その全額を請求されるリスクがあります。フリーランスが負うにはあまりに過大なリスクです。
- 対策の考え方: 一般的な契約実務では「損害賠償額の上限は、本業務の委託料を上限とする」という条項を設けることがあります。これは、受け取る報酬額のリスクに見合った責任を負うという考え方に基づいています。ただし、このような条項は必ずしも認められるわけではなく、具体的な損害賠償条項の内容や上限設定については、案件の性質や業界慣行によって適切な水準が異なるため、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
5.3 契約解除・中途解約の条件
プロジェクトの途中で契約を打ち切る際のルールです。
- フリーランスにとって非常に不利になり得る条項:
甲は、いつでも本契約を解除することができる。 - 何が問題か: クライアントの都合で、理由なくいつでも契約を打ち切られる可能性があります。プロジェクトのためにスケジュールを確保していたのに、突然仕事がなくなり、報酬も支払われないという最悪の事態に陥ります。
- 対策の考え方: 「契約を中途解約する場合は、相手方に対し、1ヶ月以上の予告期間をもって書面で通知しなければならない」といった予告期間を設けることや、「甲の都合により本契約を解除する場合、甲は乙に対し、乙が既に履行した部分の報酬及び逸失利益を賠償しなければならない」といった、フリーランス側の損害を補填する条項を求める交渉も考えられます。ただし、具体的な解除条項の内容については、案件の特性や契約期間などを総合的に考慮する必要があるため、弁護士等の専門家にご相談ください。
【参考資料】 文化庁: 著作権制度の概要 著作権の内容(著作権法第27条、第28条など)や著作者人格権について定められています。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/index.html
出典・引用:3 https://goworkship.com/magazine/outsourcing-note/4 https://topics.type.jp/type-engineer/engineer-job-market-trend/-subcontracting/
6. フリーランス契約書のチェック方法とスマートな交渉のコツ
提示された契約書にそのままサインするのは絶対にNGです。内容をしっかり吟味し、言うべきことは言う。これがプロのフリーランスの作法です。
6.1 フリーランス契約書を読むときのセルフチェックリスト
契約書を前にしたら、探偵になったつもりで以下の点をチェックしましょう。
- 当事者: 自分の名前や住所は正しいか?相手は誰か?
- 業務範囲: やるべきこと、やらなくてよいことの線引きは明確か?
- 報酬: 金額、支払日は明確か?源泉徴収や経費の扱いは?
- 知的財産権: 権利は誰のもの?ポートフォリオに載せられるか?
- 損害賠償: 上限は設定されているか?(最重要交渉ポイント!)
- 契約不適合責任: バグ修正の対応期間は妥当か?(例: 検収後3ヶ月など)
- 解除条項: 一方的に不利な条件でクビにされないか?
- 再委託: 他のフリーランスに一部業務を手伝ってもらうことは可能か?
- 管轄裁判所: 万が一裁判になった場合、どこの裁判所か?(遠方だと不利)
契約書の内容について疑問や不安がある場合は、サインする前に必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
6.2 フリーランス契約書の不明点を「確認」という形で質問する技術
疑問点を指摘する際、「この条項はおかしいです!」とトラブルを引き起こすような交渉をするのは得策ではありません。あくまで「お互いの認識を合わせたい」というスタンスで、低姿勢かつ論理的に質問しましょう。
- 悪い例: 「この損害賠償、上限なしとかありえないんですけど?」
- 良い例: 「第〇条の損害賠償の範囲について確認させてください。万が一のリスクを双方でコントロールするため、一般的な契約実務に倣い、賠償額を本業務の委託料の範囲内に限定させていただくことは可能でしょうか?」 質問と回答のやり取りは、必ずメールなど記録に残る形で行いましょう。
6.3 フリーランス契約書交渉で対立しない「提案型」の交渉術
交渉は、ゼロか100かの戦いではありません。相手の立場も尊重しつつ、お互いの落としどころを探る共同作業です。
- 代替案を用意する: 「Aは難しい」と断るだけでなく、「Aは難しいのですが、代わりにBという形ではいかがでしょうか?」と代替案を提示することで、前向きな姿勢を示すことができます。
- 理由を添える: なぜその修正が必要なのか、その背景(「フリーランスとしてのリスク管理のため」「将来のキャリア形成のため」など)を正直に、かつ簡潔に伝えることで、相手の理解を得やすくなります。
- 最後は対等なパートナー: 契約は双方が納得して初めて成立します。不当な要求を飲む必要はありません。どうしても合意できない場合は、勇気をもって「今回はご縁がなかったということで」と辞退することも、自分を守るための重要な選択です。
交渉戦略や具体的な修正提案については、弁護士等の専門家からアドバイスを受けることをお勧めします。
【参考資料】 フリーランス・トラブル110番 第二東京弁護士会が運営する、フリーランスのトラブルに関する相談窓口。実際のトラブル事例も参考になります。 https://freelance110.jp/
出典・引用:1 https://mid-works.com/columns/freelance-career/freelance-selfemployed/11414811 https://japan-design.jp/freelance/9128/
7. フリーランス向けの信頼できる契約書テンプレートの入手先
ゼロから作るのは大変なので、信頼できるテンプレートを「たたき台」として活用しましょう。
7.1 契約書テンプレートが手に入る弁護士ドットコムやクラウドサインなどの法務系サービス
弁護士が監修したテンプレートは、法的な正確性が高く、最新の法改正にも対応している可能性が高いでしょう。クラウドサインなどの電子契約サービスが提供するテンプレートは、そのまま電子契約に移行できる利便性もあります。
- クラウドサイン: テンプレートライブラリ https://www.cloudsign.jp/template/
7.2 契約書テンプレートも提供する一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
フリーランスの実態に即した、実践的なテンプレートを提供しています。会員になることで、テンプレートの利用だけでなく、賠償責任保険への加入や、法務・税務相談などの手厚いサポートが受けられます。フリーランスとして活動するなら、入会を検討する価値は非常に高いです。
- フリーランス協会 https://www.freelance-jp.org/
7.3 契約書テンプレートの参考になる中小企業庁・公正取引委員会などの公的機関
国が提供するモデル契約書は、特定の企業に有利になることがなく、公平な立場で作成されているのが特徴です。契約書の基本的な考え方や構成を学ぶための「教科書」として非常に優れています。
- 中小企業庁: 各種契約書等の参考例 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/hensyu.htm
出典・引用:3 https://tech.hipro-job.jp/column/7902 https://tng-marketing.com/freelance/knowledge/contract/
8. フリーランス契約書がない場合の緊急対応策
理想は契約書ですが、どうしても締結できない場合でも、諦めてはいけません。契約書がない状態は非常にリスクが高いため、あくまで応急措置として、最低限のリスク対策で証拠を残しましょう。
8.1 フリーランス保護新法を盾に「取引条件の明示」を求める
施行済みの「フリーランス保護新法」では、発注者はフリーランスに対し、以下の取引条件を書面やメール等で明示することが義務化されています。
- 業務内容
- 報酬額
- 支払期日
- その他(公正取引委員会規則で定める事項)
この法律を根拠に、「法律で義務付けられておりますので、お手数ですが、以上の点についてメールにてご提示いただけますでしょうか?」と、丁寧かつ毅然とした態度で明示を求めてみましょう。これはあなたの正当な権利です。
8.2 契約書代わりに発注書・請求書を「合意の証拠」として活用する
- 発注書(注文書): クライアントから、業務内容、金額、納期が記載された発注書を発行してもらい、必ず保管します。
- 請求書: こちらから送る請求書にも、実施した業務内容を具体的に記載し、控えを保管します。 これらの書類は、直接的な契約書ではなくても、双方の合意があったことを推認させる重要な証拠となります。
8.3 業務開始後でもフリーランス契約書(基本契約)の締結を提案する
すでに業務が始まっていても手遅れではありません。特に、長期的な取引になりそうな場合は、「今後の取引をより円滑に進めるため、この機会に基本契約書を締結させていただけませんでしょうか」と提案してみるのがおすすめです。誠実なクライアントであれば、双方のメリットを理解し、応じてくれるはずです。
【参考資料】 内閣官房: 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 フリーランス保護新法の背景や目的が記載されています。 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/
出典・引用:4 https://note.com/kokoro_rosca/n/n3cf79ecf0a7a5 https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/
ここまで見てきたように、契約書まわりのリスクだけでもかなりのボリュームがありますが、実際のフリーランスエンジニアの現場では、収入・案件獲得・税務・スキル・健康など、契約以外のリスクも同時に襲ってきます。フリーランスという働き方に潜む代表的なリスク全体とその対策を俯瞰したい方は、こちらのコラムもあわせてご覧ください。
9. フリーランス契約書に関する「駆け込み寺」
一人で悩まないでください。契約に関する不安やトラブルは、専門家の力を借りるのが最も確実で早い解決策です。
9.1 フリーランス契約書トラブルは弁護士への相談(トラブル予防&解決のプロ)
契約書のリーガルチェック(法的な問題がないかの確認)や、トラブル発生時の交渉・訴訟代理は、弁護士の独壇場です。高額な案件や長期にわたる契約を結ぶ前に、数万円の費用をかけてでもリーガルチェックを受けることは、将来の数百万、数千万円の損失を防ぐ最高の「保険」になります。契約書に関する疑問や不安がある場合は、遠慮なく弁護士にご相談ください。これは決して大げさなことではなく、プロのフリーランスとして当然の備えです。
- 日本弁護士連合会: ひまわりサーチ https://www.bengoshikai.jp/
9.2 フリーランス契約書の相談先:フリーランス協会・下請かけこみ寺
弁護士に相談するのは敷居が高いと感じる場合、まずはこうした専門窓口に相談してみましょう。
- フリーランス協会: 会員向けに、弁護士による無料相談(初回)や、トラブル対応のノウハウを提供しています。
- 下請かけこみ寺: 国が全国に設置している無料で相談できる窓口。中小企業庁が管轄しており、取引上の悩みに専門の相談員が対応してくれます。
9.3 フリーランス契約書とお金・働き方の相談ができる税理士・社労士(お金と働き方の専門家)
- 税理士: 報酬の税務処理(確定申告、消費税、インボイス制度)に関する相談。
- 社会保険労務士(社労士): 契約内容によっては、実態が「雇用」とみなされ、社会保険への加入義務が発生する場合があります。そうした「偽装フリーランス」のリスクがないか、働き方に関する相談ができます。
税理士: 報酬の税務処理(確定申告、消費税、インボイス制度)に関する相談。確定申告の基本や経費・青色申告の考え方をあらかじめ自分でも整理しておきたい方は、フリーランス確定申告、経費・青色申告で損してない? もあわせてチェックしておくと、税理士への相談がスムーズになります。
出典・引用:2 https://freeconsultant.jp/column/c223-2/
フリーランスという働き方は、大きな自由と可能性を秘めています。その自由を最大限に享受し、プロフェッショナルとして輝き続けるために、契約書という武器を使いこなし、あなた自身の価値と権利をしっかりと守り抜いてください。このコラムが、その第一歩となれば幸いです。
出典・引用:
- https://mid-works.com/columns/freelance-career/freelance-selfemployed/1141481
- https://freeconsultant.jp/column/c223-2/
- https://tech.hipro-job.jp/column/790
- https://note.com/kokoro_rosca/n/n3cf79ecf0a7a
- https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/
- https://mattock.jp/blog/ai-chatbot/freelance-contract-conditions/
- https://japan-design.jp/freelance/9128/
- https://tng-marketing.com/freelance/knowledge/contract/
- https://goworkship.com/magazine/outsourcing-note/
- https://topics.type.jp/type-engineer/engineer-job-market-trend/-subcontracting/
- https://biz.moneyforward.com/contract/basic/9279/
出典
- https://japan-design.jp/freelance/9128/
- https://tng-marketing.com/freelance/knowledge/contract/
- https://goworkship.com/magazine/outsourcing-note/
- https://topics.type.jp/type-engineer/engineer-job-market-trend/-subcontracting/
- https://biz.moneyforward.com/contract/basic/9279/
- https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/contract-9points/
- https://tech-stock.com/magazine/attention-point-of-contract/
- https://krow.co.jp/media/archives/2491
- https://freelance-hub.jp/column/detail/676/