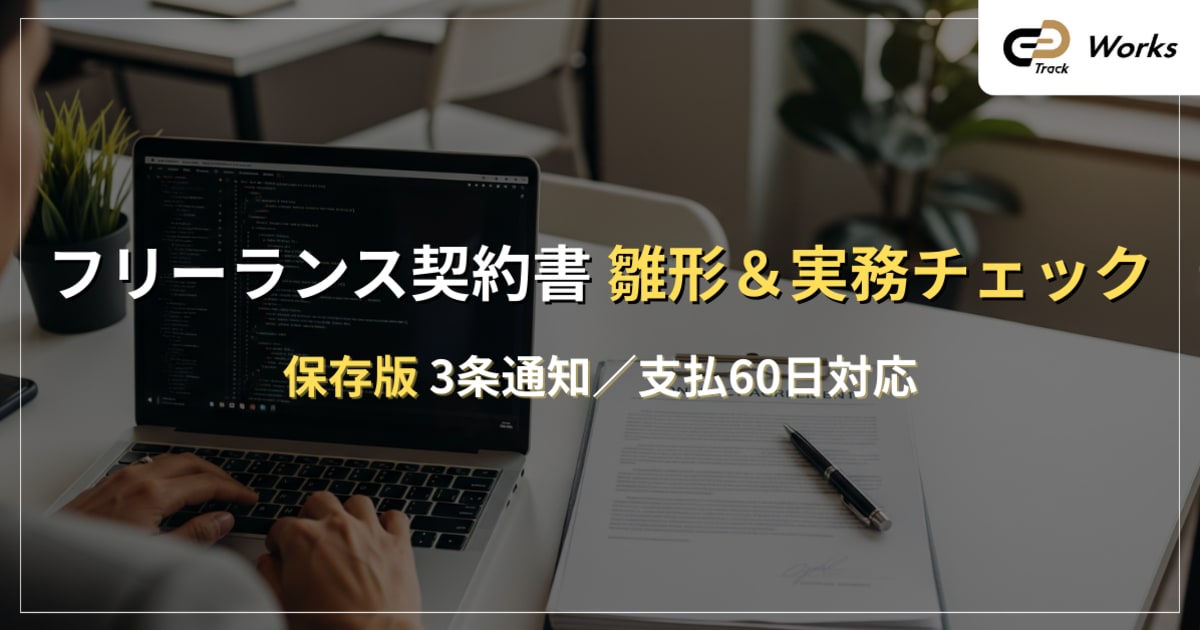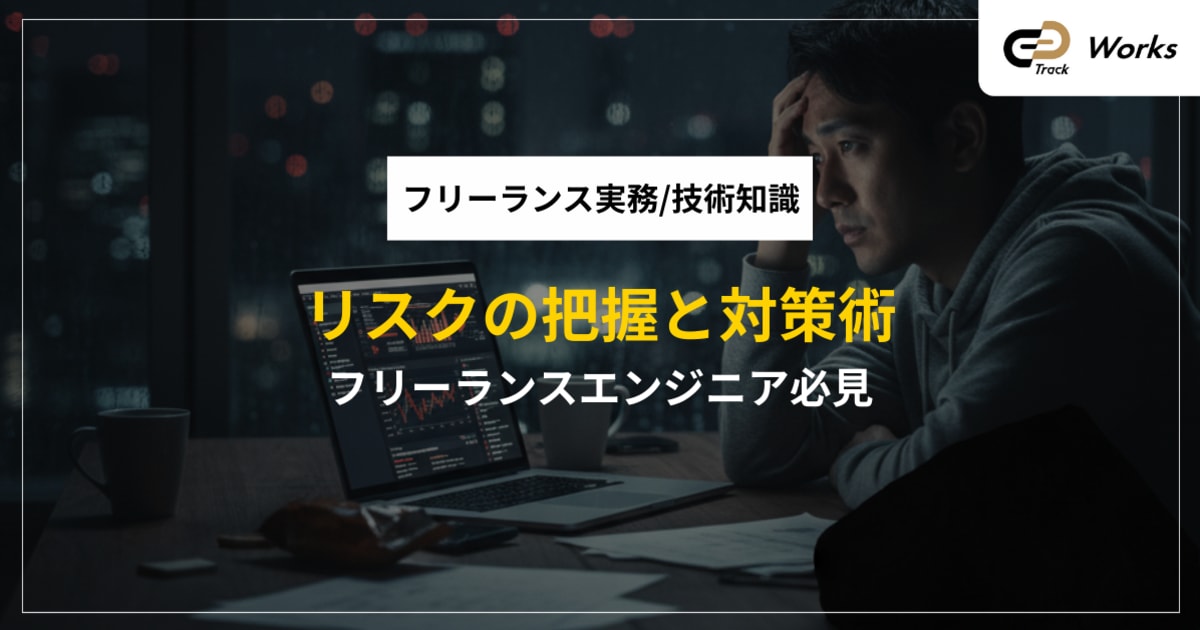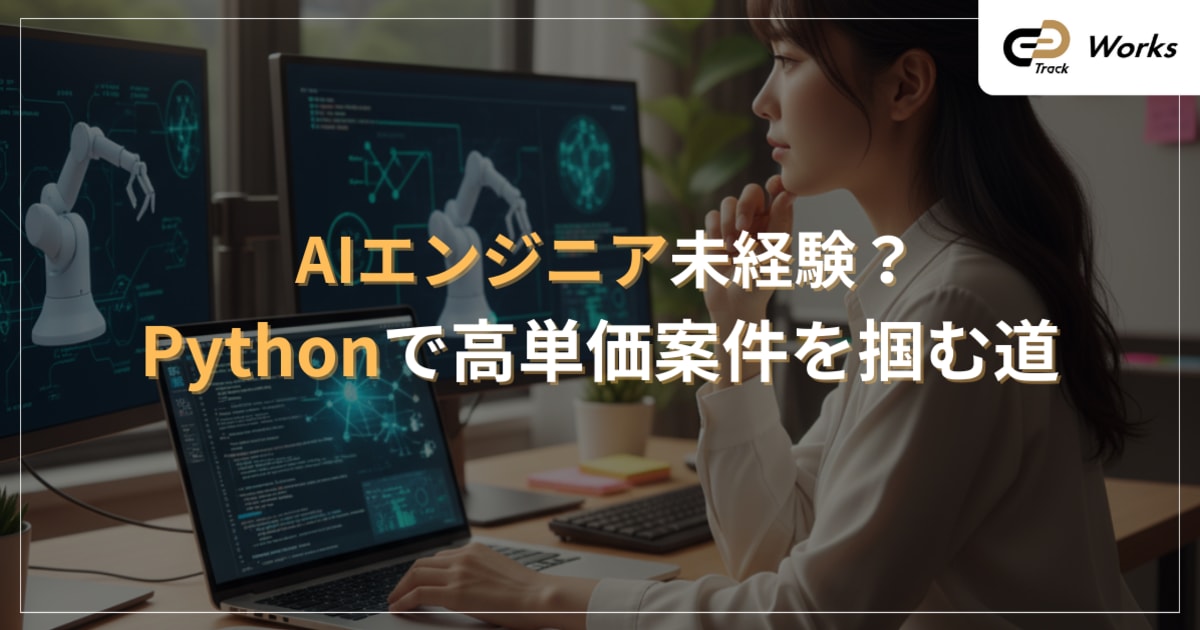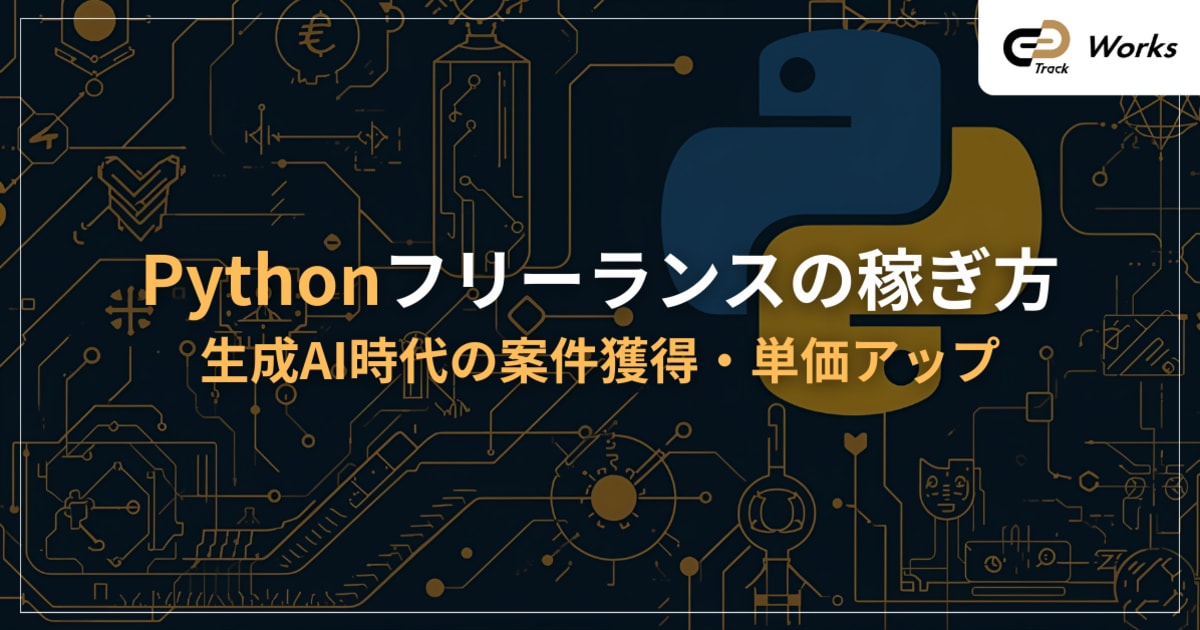はじめに:業務委託契約書の雛形で押さえる重要ポイントをざっくり整理
フリーランスエンジニアとして活動する上で、業務委託契約書は自分を守る最重要ツールです。さらに2024年11月1日施行の「フリーランス新法」により、取引条件の明示(いわゆる3条通知)や支払期日など、契約で押さえるべき基準がより明確になりました。
ただ、問題はここからです。ルールを知っていても、毎回ゼロから契約書を作ると抜け漏れが起きます。そこで本記事では、実務で使える「業務委託 契約書 雛形(ミニ雛形)」を軸に、案件ごとに何を埋め、どこを交渉し、どう運用すると安全になるのかをチェックポイント形式で整理します。
契約前の「取引条件の明示(フリーランス新法3条)」は相手(発注者)の義務です。あなたは着手前に必ず受領しましょう。 明示は口頭では足りず、書面または電磁的方法(メール・SNS等)で行う必要があります。明示事項は「給付内容・報酬額・支払期日」等を含む(条件付き項目を含めて整理すると9項目)ため、契約書で兼ねる場合も“漏れなく”埋めることが重要です。
支払期日は「検収完了から30日以内」を基本提案できます(法の上限は60日以内)。6か月以上の継続契約を解除・不更新する場合は、30日前予告が原則となりました(例外あり)。電子契約はコスト削減につながります(原則として印紙税は課税対象外)が、紙で正式文書として扱う場合は課税対象となる可能性があります。
それでは、雛形を手元に置いた上で、実務で使える契約の作り方を具体的に見ていきましょう。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。運用は取引内容で変わります。
根拠:フリーランス新法の概要は公正取引委員会(特設)を参照。
フリーランス新法の概要:業務委託契約書で押さえる変更点
まず、今回の法改正の正式名称と施行日を確認しておきましょう。
正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法/令和5年法律第25号)
施行日:2024年11月1日
あわせて「フリーランス・ガイドライン」も2024年10月18日に改定されています。
【出典・参考】
1. なぜ業務委託契約書の雛形(+3条通知)が必須なのか
業務委託は、**「作る・直す」より先に「決める・残す」がないと、ほぼ確実に揉めやすくなります。
特にフリーランスのエンジニア案件は、途中で仕様が揺れたり、検収が伸びたり、成果物の権利が曖昧になりやすいので、“曖昧さがコストになる構造”**を最初に潰しておくのが大切です。
そのために役立つのが、毎回ゼロから書かずに使える 「業務委託 契約書 雛形」(テンプレ)と、着手前の条件明示である 3条通知 です。
雛形は「便利だから」ではなく、**あなたの取り分と時間を守るための“論点漏れ防止装置”**として持っておくのが実務的です。
1.1 雛形がないと、交渉が“感覚”になりやすい(=負け筋が増えます)
契約交渉が苦しいのは、あなたの交渉力の問題というより、争点が整理されないまま会話が進むから起きがちです。
雛形があると、最低限ここだけは埋める、という順番が作れます。
- 業務範囲:どこまでが含まれて、どこからが追加か
- 検収:合否の基準・期限・「連絡がない場合」の扱い
- 支払い:起算日(受領日/検収日)・期日(いつ払うか)
- 権利:コードや成果物の帰属、ポートフォリオ利用の可否
- 変更:仕様変更の手順(追加見積→合意→着手)
逆に雛形がないと、話が「いい感じにお願いします」で始まり、後から揉めたときに**“何を合意していたか”を証明しにくい**です。
1.2 契約が薄いと起きやすい「3つの事故」(エンジニア案件の典型)
事故①:仕様が増えても“追加扱い”にならない(スコープが無限に広がる)
「ちょっとだけ」「軽微な修正」という言葉は、プロジェクトが苦しくなる入口になりがちです。
雛形で “やる/やらない” と、追加時の手順(例:チケット合意→再見積→書面合意)を固定しておくと、追加稼働が飲み込まれにくくなります。
事故②:検収が伸びて、支払いが先延ばし(キャッシュが詰まる)
納品したのに「確認中です」が続くと、生活防衛が一気に苦しくなります。
ここは 検収期限 と みなし検収、さらに 支払期日の起算日(検収完了日=受領日など)をセットで書けるかが分かれ目です。
事故③:成果物の権利が“全部相手”になる(ポートフォリオ・再利用が封じられる)
契約が薄いと、後から「全部弊社のものです」と言われても反論材料が残りにくいです。
ソースコードや設計書の帰属、二次利用、ポートフォリオ掲載(匿名・画面のみ等)を、**条項として“先に言語化”**しておくと安全です。
1.3 3条通知は「お願い」ではなく、着手前に“条件を残す”ための制度です
フリーランス新法では、発注者は業務開始前を前提として、取引条件を**書面または電磁的方法(メール・SNS等)**で明示する義務があります(口頭だけでは足りません)。
明示事項は次の 8項目(うち、取引によって追加で必要になる項目あり)として整理されています。
- 給付の内容
- 報酬の額・支払期日(支払日は“特定できる形”が必要)
- 当事者の名称
- 業務委託をした日
- 受領日/役務提供を受ける日
- 受領場所/役務提供を受ける場所
- (検査がある場合)検査完了期日
- (現金以外で支払う場合)支払方法に関する事項
この3条通知は、業務委託契約書で兼ねることもできますが、現場では「メールで条件提示→契約書に反映」で進むことも多いです。
どちらでもいいので、あなたとしては “条件が残っている状態で着手する” を守っていただくのが一番効果が出ます。
1.4 「条件が十分に示されていない」が約4割:だから雛形が“保険”になります
中小企業庁の調査(令和4年度)では、業務開始前に取引条件が形に残る方法で
「示されているが不十分」17.6%+「示されていない」20.7%=合計38.3% という結果が出ています。
つまり、体感ではなくデータとしても、条件が薄いまま始まる案件は珍しくありません。
だからこそ、あなた側で「雛形に沿って、最低限の論点を埋める」運用が、未払い・炎上・手戻りの確率を下げてくれます。
1.5 最小の実務ルール:着手前にこの3点が揃うと安心です(雛形に落とし込む)
難しいことを全部やろうとすると続かないので、まずは着手前に次の3点だけでも揃えていただくと、事故率が大きく下がります。
- 業務範囲:成果物/対応範囲/除外範囲(追加時の扱いも)
- 検収:合否基準・期限・みなし検収の有無
- 支払い:起算日(受領日=検収完了日など)と支払期日(60日以内の範囲で“計算できる形”)
この3点は、あなたが「細かい人」になるためではなく、プロジェクトを安全に回すための最低限の整備です。
雛形は、その整備を“毎回同じ品質で”やるために使うもの、という位置づけにしておくとブレにくいと思います。
出典・参考
- 中小企業庁:令和4年度フリーランス実態調査結果(PDF)
- 中小企業庁:フリーランス・事業者間取引適正化等法(概要・ガイドライン等)
- 公正取引委員会:フリーランスの取引適正化に向けた取組(フリーランス法NAVI等)
- 公正取引委員会:ガイドライン改定(2024年10月18日)
- 公正取引委員会:フリーランス・事業者間取引適正化等法 パンフ(PDF)
2. フリーランス新法の基礎:業務委託 契約書 雛形に関わるルールをやさしく整理
この章では、「フリーランス新法で“契約書まわり”が何を求められているのか」を、
業務委託 契約書 雛形にそのまま落とし込める形で整理します。
法律を丸暗記する必要はありません。
重要なのは、雛形の空欄に「なぜ・何を書くべきか」を理解した状態で埋められることです。
- 準委任:成果物の完成ではなく「業務の遂行」が中心(稼働・運用・保守など)
- 請負:成果物の完成が中心(納品物・完成責任が重く、検収ややり直し条件が争点になりやすい)
※検収・契約不適合責任(旧:瑕疵)・やり直し範囲は特に揉めやすいため、基礎は別記事で整理しています。
→ フリーランス 契約リスク管理|未払い・検収・瑕疵の考え方
2-1. ほぼ全ての一人フリーランスが対象
フリーランス新法は、「フリーランス(受注側)」と「発注者(事業者)」の取引を対象にしています。
受注側(あなた)
- 個人事業主で従業員を使っていない
- もしくは、代表者1名のみ・従業員なしの法人
上記に該当する場合、あなたは 「特定受託事業者」 に該当します。
つまり、一人で活動しているフリーランスエンジニアの方は、ほぼ対象になります。
発注側(クライアント)
- 従業員を使用している企業
- 役員が複数いる法人 など
こちらは 「業務委託事業者/特定業務委託事業者」 に該当します。
実務的には、相手が企業であれば新法前提で考えておく方が安全です。
✅ 2-2. 3条通知(業務委託契約書 雛形でも兼ねられる取引条件明示)とは何か
3条通知とは、フリーランスに業務委託をする場合に、
発注者が 業務開始前を前提として、取引条件を
書面または電磁的方法(メール・SNSメッセージ等)で明示する義務です。
※口頭のみは要件を満たしません。
ポイントは、「立派な契約書を必ず作ること」ではなく、
着手前に“条件が確認できる形で残っている状態”を作ることです。
実務では、次の流れが最も回しやすいケースが多いです。
- メール等で3条通知(条件提示)
- 内容を確認したうえで業務委託契約書を締結
3条通知で明示する事項(9項目)
- 給付の内容(成果物・提供サービスの内容)
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日(納品日・作業完了日)
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- (検査をする場合)検査完了日
- (現金以外で支払う場合)報酬の支払方法に関する事項
雛形に落とす際の注意点(ここが薄いと揉めます)
特に注意したいのは、次の項目です。
- 給付内容
- 「Webアプリ開発」ではなく、機能単位で具体化
- 例:認証機能、管理画面、API実装、テスト、ドキュメント作成
- 除外作業(デザイン、インフラ構築、運用監視など)も明記
- 受領日・検査完了日
- 納品後◯営業日以内に合否連絡
- 期限内に連絡がない場合はみなし検収
- 支払期日
- 「翌々月末」など曖昧な表現は避け、
起算日+◯日以内 または 具体日で記載
- 「翌々月末」など曖昧な表現は避け、
※3条通知のお願い文・催促テンプレは後半にまとめる想定です。
→ ステップ2:3条通知テンプレにジャンプ
2-3. 支払いルール(業務委託契約書で最重要ポイント)
フリーランス新法では、報酬の支払期日は原則として、
「給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内」
で定める必要があります。
「受領日」はいつになるのか?
エンジニア案件では、成果物が情報(ソースコード・設計書等)であることが多いため、
実務では 「検収合格日=受領日」 として整理するのが一般的で、トラブルも少なくなります。
支払期日の書き方(雛形向け)
おすすめ
- 検収合格日から30日以内
- 月末締め翌月末支払(※60日を超えない設計)
避けたい例
- 「翌々月末」のみ(60日超のリスク)
- 「納品後2か月以内」など計算しづらい表現
再委託(下請け)が絡む場合の特則
再委託案件では、3条通知で以下を明示した場合に限り、
- 再委託である旨
- 元委託者の名称
- 元委託者の支払期日
「元委託支払期日から30日以内」 で支払期日を定める特則が使えます。
2-4. 長期の業務委託(6か月以上)の解除・不更新ルール
6か月以上の継続契約については、解除・不更新に関して特別な保護があります。
- 原則:30日前までに予告が必要
- フリーランスが理由開示を求めた場合:発注者は理由を説明する義務
例外として、以下の場合は30日前予告が不要になることもあります。
- 災害など、やむを得ない事情
- 元請契約の解除に伴う再委託終了
- 短期契約であることが明らかな場合
雛形では
「30日前予告」を基本としつつ、
「法令の定めに従う」と補足しておくと運用しやすくなります。
2-5. 業務委託と雇用契約の違い(偽装請負の注意点)
注意すべき点は、契約書の名称ではなく「実態」で判断されるという点です。
以下のような状態が重なると、
業務委託でも 派遣・雇用に近いと判断されるリスクがあります。
- 毎日決まった時間に出社し、勤怠・休暇を管理される
- 作業手順・優先順位まで日常的に細かく指示される
- 社員と同じ指揮命令系統・評価体制に組み込まれている
雛形でできる現実的な対策
- 作業方法・手段は受注者の裁量と明記
- 指示は「成果物・期限・要件」中心に限定
- 準委任でも、稼働上限・成果定義(レポート・レビュー成果)を設定
出典・参考
3. 業務委託契約書の雛形で押さえる必須項目(実務メモつき)
フリーランスの契約トラブルって、だいたい「作業が始まってから発覚するズレ」が原因になりやすいです。
なので 業務委託 契約書 雛形は、“法務っぽい書類”というより ズレを先に潰すためのチェックリストとして持っておくのが実務的だと思います。
特に揉めやすいのは、次の3つです。
- 業務範囲:どこまでが契約内で、どこからが追加か
- 検収:合否の基準・期限・連絡がない場合の扱い
- 支払期日:起算日(受領日/検収日)と、いつまでに払うか
3.0 まず“最低限”として雛形に入れておきたい項目(抜けると不利になりやすい)
以下が抜けていると、後で揉めたときに一気に不利になりやすいです(特に支払期日・業務範囲・検収)。
- 取引当事者の名称(発注者/受注者)
- 業務内容(成果物/役務の範囲)
- 成果物の納期・役務の提供日(または期間)
- 納品方法・納品先(データ/場所)
- 検収の有無、検収の期限・基準(みなし検収も含む)
- 報酬額(算定方法・税・精算条件)
- 支払期日(起算日+期限)
- 支払方法(振込など)+振込手数料負担
実務では「本文に全部書く」のがしんどいので、
“本文はルール”、詳細は“別紙(仕様・スコープ・受入基準)” に寄せると回しやすいです。
根拠・参考(公式)
3-1. 業務内容・範囲(「やる/やらない」を雛形で固定)
業務内容は、契約書の中でも特に重要な部分だと思います。
ここが曖昧だと、あとから「それも当然やってもらえる前提でした」と言われやすく、追加作業が飲み込まれがちです。
雛形に入れると強い“5点セット”
- 成果物(Deliverables):何を納品するか(コード、設計書、テスト、手順書など)
- 作業範囲(Scope):実装する機能・対応するチケットの範囲
- 除外範囲(Out of Scope):やらないこと(例:デザイン、インフラ、CS、運用監視)
- 前提・依存(Assumptions / Dependencies):発注者側で用意が必要なもの(アカウント、仕様確定、素材提供)
- 完了条件(Done):どこまでやれば「完了」とするか(最低限の受入基準)
書き方のコツ(エンジニア案件向け)
- 「Webアプリ開発」より 機能単位にしていただくと、追加見積の線引きがしやすいです
例:ユーザー管理(新規登録/ログイン/パスワード再設定)、管理画面、API、ログ出力 など - “やらないこと”は遠慮せず書いて大丈夫だと思います(むしろ双方に優しいです)
コピペ用:スコープ定義(別紙A)ミニ雛形
※そのまま契約本文に入れるより、別紙にして更新しやすくするのが現実的です。
別紙A:仕様・スコープ(抜粋)
- 含む(Scope)
- 例)ユーザー管理機能(新規登録/ログイン/パスワードリセット)の実装
- 例)管理画面(一覧/詳細/編集)の実装
- 例)単体テストの追加(主要ロジック)
- 例)README/簡易手順の整備(起動方法、環境変数一覧)
- 含まない(Out of Scope)
- UIデザイン作成、コピーライティング
- インフラ構築・本番運用監視(別途契約)
- CS対応、データ移行(別途見積)
- 前提(Assumptions)
- 発注者がリポジトリ/クラウド/必要アカウントを提供する
- 仕様確定は○月○日までに行う(未確定部分は別途合意)
- 検証環境・テストデータは発注者が提供する
- 追加作業の扱い
- 上記に含まれない変更は、チケット起票 → 影響確認 → 追加見積 → 書面合意後に着手する
3-2. 報酬・支払条件(支払期日と検収をセットで)
「いくら払うか」だけではなく、いつ・何を条件に・どう払うかまで決めておくのがポイントだと思います。
ここが薄いと、検収が伸びた瞬間に、あなたのキャッシュフローだけが苦しくなりやすいです。
報酬方式ごとの“最低限”の書き分け
- 固定報酬(請負寄り)
- 総額/分割条件(マイルストーン)/検収条件/追加変更の扱い
- 時間単価(準委任寄り)
- 単価/月の上限(例:140h)/超過時の精算(15分単位など)/稼働報告方法
- マイルストーン払い
- 支払トリガー(どの成果で請求できるか)/部分検収の可否/中止時の精算ルール
“支払期日”は「起算日+期限」が計算できる形だと強いです
法令上、支払期日は 受領日から60日以内で、できる限り短い期間内で定めることが求められています。
実務では、検収があるなら 「検収合格日=受領日」 に寄せておくと揉めにくいと思います。
- おすすめの書き方例
- 「検収合格日(受領日)から30日以内に支払う」
- 月次運用なら、60日を超えない設計で 「月末締め翌月末払い」 など
“検収”は支払いとセットで(みなし検収が効きます)
検収が曖昧だと「確認中」で止まり続けるので、以下は雛形に入れておくと安心です。
- 検収の期限(例:納品後5営業日以内)
- 合否の通知方法(例:メール/チケットでの通知)
- 期限内に連絡がない場合の扱い(=みなし検収)
- 不合格時の是正範囲(=仕様に対する不適合だけなのか、追加要望まで含むのか)
コピペ用:報酬・支払+検収(短文)
- 支払:報酬は、検収合格日(受領日)を起算日として 30日以内に支払う。支払方法は銀行振込とする。
- 検収:発注者は納品後 5営業日以内に合否を通知する。期限までに通知がない場合、検収合格とみなす。
- 手数料・税:振込手数料の負担者(発注者/受注者)および消費税の取扱いを明記する。
3-3. 納期・場所・時間(稼働の期待値を合わせる)
納期と稼働のズレは、炎上の原因になりやすいです。
「いつまでに何を」「週何日くらい」「どの時間帯で連絡がつくか」を最低限そろえておくと、後半がかなり楽になります。
アジャイル(スプリント)なら“運用ルール”を先に決める
- スプリント長(例:2週間)
- 毎スプリントの成果(デモ/リリース/PR単位)
- バックログの確定タイミング(いつ確定するか)
- 優先順位の決め方(誰が決めるか)
- 緊急割り込みの扱い(対応する/別見積)
リモート前提でも書いておくと助かる項目
- 作業場所:原則リモート、必要時のみ出社(頻度の目安)
- コアタイム:平日○時〜○時は連絡可能
- 定例:週1回30分、議題は前日までに共有
- コミュニケーション:Slack/Teams/メール/チケット(どれを正とするか)
3-4. 成果物・知的財産権(コードの帰属・二次利用まで)
ここは「揉めたら取り返しがつきにくい」ので、できれば雛形で先に型を作っておきたいです。
特にエンジニアだと、コードの一部に汎用ライブラリ(再利用したい資産)が混ざることが多いので、丸ごと譲渡だと将来の動きが縛られやすいです。
争点になりやすいポイント
- 著作権(譲渡か、利用許諾か)
- 汎用部分(テンプレ、共通関数、ライブラリ)の扱い
- ポートフォリオ掲載(匿名・画面だけ・期間制限など)
- OSS利用時のライセンス遵守(表示義務、同梱物、改変の公開義務など)
- 生成AI利用(利用可否、成果物の権利・第三者権利侵害の扱い)
コピペ用:知財の落としどころ(例)
- 成果物の著作権は(発注者に譲渡/発注者に利用許諾)する。
- ただし、受注者が従前から保有するノウハウ・汎用ライブラリ・テンプレートは受注者に留保する。
- 受注者は、機密情報を除いた範囲で、成果物をポートフォリオ目的で利用できる(事前承諾/匿名化等の条件付き)。
3-5. 機密保持(NDA)
NDAは「秘密にします」だけだと弱く、運用が詰まりがちです。
エンジニア案件では、リポジトリ・クラウド・ログ・テストデータなど、“どこに何が残るか”が増えるので、削除・返還のルールまで決めておくと安心です。
雛形で明確にしたいポイント
- 機密情報の定義(口頭情報を含むか)
- 目的外利用の禁止(その案件以外に使わない)
- 再委託先へ同等義務(外注するなら必須)
- セキュリティ措置(MFA、端末暗号化、持ち出し禁止など)
- 契約終了時の返還・削除(期限と方法)
- インシデント時の通知(漏えい疑い含む)
コピペ用:返還・削除の一文(例)
- 契約終了後30日以内に、受注者は機密情報を返還または削除し、求めがあれば削除完了を報告する。
3-6. 契約変更・解除(変更手順を型にする)
仕様変更は“起きるもの”なので、起きたときに揉めない手順を先に決めておくのが一番効きます。
変更手順(おすすめの型)
- **チケット(変更要求)**を起票
- **影響範囲(工数・納期・費用)**を提示
- 追加見積
- 書面(メール等)で合意
- 着手
ここがないと「とりあえずやって」が増えやすいので、雛形に“必ず合意してから”を入れておくと楽になります。
解除・終了の条件(実務で揉めやすいところ)
- 30日前予告(長期契約なら特に)
- 即時解除できる条件(重大な違反、支払遅延など)
- 中途終了時の精算(どこまでが支払対象か)
- データ返還/アクセス権の削除手順(クローズ手順)
3-7. 損害賠償(責任上限は“推奨の防御条項”)
損害賠償の上限は必須条項ではありませんが、フリーランス側の防御としてはかなり効きやすいです。
特に、発注者雛形だと「間接損害も含め無制限」みたいな設計が紛れていることもあるので、ここは確認していただきたいです。
よくある調整ポイント
- 責任上限:契約金額、または直近○か月分の支払総額など
- 間接損害の除外:逸失利益、特別損害など
- 例外:故意・重過失は除外(上限を外す)など
- データ損失:バックアップ責任の分担(どちらが何を担うか)
コピペ用:責任限定(例)
- 当事者の故意または重過失による場合を除き、受注者の損害賠償責任の総額は、直近6か月間に支払われた報酬総額を上限とする。
- 逸失利益その他の間接損害は賠償対象外とする。
3-8. 管轄裁判所・準拠法
揉めないのが一番ですが、万が一のときに「どこで争うか」が決まっていないと、それだけでコストが増えやすいです。
実務での考え方(目安)
- 遠方の発注者だと、相手地裁に固定されると移動コストが重い
- なので「どちらが現実的か」を基準に、落としどころを探すのが良いと思います
- 可能なら、訴訟の前に協議(一定期間)を挟む条項もあるとソフトに始めやすいです
コピペ用:管轄(例)
- 本契約に関する紛争については、当事者間で誠実に協議し、解決しない場合、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この章のまとめ(雛形を“強くする”最短手順)
もし全部は大変そうでしたら、まずは次の3つだけでも雛形で固定していただくと、事故率が下がりやすいです。
- スコープ(含む/含まない/前提)
- 検収(期限+みなし検収)
- 支払(起算日+期日)
出典・参考
4. エンジニア案件の業務委託契約書で追加したいポイント(雛形を“エンジニア仕様”にする)
一般的な業務委託 契約書 雛形だけでも最低限は回せますが、エンジニア案件は「技術的な前提」がズレた瞬間に、工数・納期・責任が一気に崩れやすいです。
そこでこの章では、雛形に**“技術の実務ルール”を追加する観点**をまとめます。
(ポイントは、法律論ではなく 現場で揉めやすい所を先に文字化することだと思います)
4-1. 技術要件の明確化(言語・FW・バージョンまで)
エンジニアリング案件では、契約書本文に「開発する」だけ書いても、実務だと情報が足りないことが多いです。
業務委託 契約書 雛形に追記するなら、最低でも「環境差分で揉める要素」を固定しておくと安心です。
1) 技術スタックは“バージョンまで”を基本にする
例として、次のように 具体のバージョンまで揃えておくと、環境違いによる手戻りが減りやすいです。
- 開発言語:Python 3.10+
- フレームワーク:Django 4.2
- DB:PostgreSQL 14
- デプロイ先:AWS(EC2 / ECS / Lambda など)
- IaC:Terraform ○○ / CloudFormation ○○(使うなら)
- CI/CD:GitHub Actions / GitLab CI / CircleCI 等(どれが正か)
- パッケージ管理:pip / poetry / npm / pnpm(固定したい場合)
実務では、本文に細かく書くより
別紙(技術仕様書)で固定し、契約本文は「別紙に従う」で受けておくと更新が楽です。
2) 「どこまでが受注者の責任か」を技術観点で線引きする
雛形のままだと曖昧になりやすいので、次を明確にしておくのが効きます。
- 受注者がやる:アプリ実装/テスト追加/PR作成/レビュー対応
- 発注者がやる:クラウド契約/本番デプロイ権限付与/監視/インフラ変更
- 共同:障害対応の一次切り分け(誰が初動するか)
3) セキュリティ要件は「運用ルール」に落とす
“セキュリティに配慮する”の一文だと弱いので、次のように運用に落とした記載があると事故りにくいです。
- 本番アクセス:発注者提供VPN経由のみ/IP制限あり
- 認証:MFA必須
- 鍵管理:個人端末に秘密鍵を保存しない(可能ならVault等)
- 権限:最小権限(必要な期間だけ付与)
- 端末:ディスク暗号化/画面ロック/共有端末禁止
- データ:持ち出し禁止/検証用はマスキングデータ
コピペ用:技術仕様(別紙)ミニ雛形
別紙B:技術要件(例)
- 言語:____(例:Python 3.10+)
- FW:____(例:Django 4.2)
- DB:____(例:PostgreSQL 14)
- インフラ:____(例:AWS ECS / RDS)
- CI:____(例:GitHub Actions)
- コーディング規約:____(例:Black / Ruff / ESLint など)
- 環境:dev / stg / prod(責任分界:____)
- セキュリティ:MFA必須/VPN経由/最小権限/ログ持ち出し禁止 など
- 重要:上記が変更される場合は、変更手続(4-3)に従い追加合意の対象とする
4-2. 品質・レビュープロセス(受入基準と揃える)
品質の話は、気合いで乗り切ろうとすると最後に破綻しがちです。
なので、業務委託 契約書 雛形には「品質をどう判定するか(=受入基準)」を先に置けると、納品時の揉め事が減りやすいです。
1) “開発中の基準”と“検収基準”を一致させる
開発中は「Lint通ってます」で進めていたのに、検収で「テストが足りない」と言われると揉めます。
そこで、受入基準(検収基準)を、できれば 測定可能な条件にしておくのがよいと思います。
- 静的解析:lint/format をCIで必須(例:ESLint/Prettier, Ruff/Black など)
- テスト:ユニットテスト実行がCI必須(カバレッジは“目安”にして例外運用も可)
- ビルド:CIで build 成功が必須
- セキュリティ:依存関係スキャン(Snyk等)を入れるかどうか
- 受入:指定のE2E手順(チェックリスト)を満たす
カバレッジ80%のような数値は強い反面、例外が出やすいので、
「原則○%を目安。ただし合理的理由がある場合は協議」など、運用余地がある方が回ることも多いです。
2) レビュー回数・マージ条件を先に決める
レビューが無限に伸びると納期が死ぬので、最低限のルールを置けると安心です。
- PRは最低1名レビュー(誰がレビューするか)
- マージ条件:CIグリーン+承認+コンフリクト解消
- レビュー期限:レビューは原則○営業日以内(遅延時はスプリント計画を調整)
- 手戻り範囲:受入基準を満たすまで(仕様変更は4-3へ)
3) 検収(受入)と支払の接続を“仕組み”にする
検収の合否連絡が止まると支払いも止まりやすいので、以下をセットにしやすいです。
- 検収期限:納品後○営業日以内
- 期限までに連絡がない場合:みなし検収
- 不合格の条件:仕様書・受入基準との不一致に限定(好みの要望は変更扱い)
コピペ用:Definition of Done(受入基準)例
別紙C:受入基準(DoD)
- CIが成功していること(lint/test/build)
- 指定の受入チェックリスト(____)を満たすこと
- 主要機能の動作確認が完了していること(ブラウザ/API等)
- 重大バグ(Severity High以上)が残っていないこと(定義:____)
- ドキュメント(README/手順)を更新していること(対象:____)
4-3. 仕様変更への対応(アジャイル開発の“追加合意”)
アジャイル開発は変更が前提なので、契約で「変更の手続」がないと、だいたいどこかで破綻します。
業務委託 契約書 雛形に追加するなら、ここは“事故防止の心臓部”だと思います。
1) 変更フローは「合意の順番」を固定する
おすすめの型は、次の順番です(口頭合意を避けやすいです)。
- バックログ(チケット)起票
- 影響分析(工数・納期・費用・品質への影響)
- 再見積(ポイント/人日/金額のいずれか)
- 追加合意(メール等の書面でOK)
- 着手
2) “軽微な修正”の線引きは、必ず定義しておく
軽微の定義がないと、軽微が無限に増えます。
現場で使いやすいのは、時間で区切るやり方です。
- 軽微な修正:1人日以内(または2時間以内など、案件に合わせる)
- それを超える:追加見積の対象
ただし、時間定義だけだと揉めることがあるので、内容でも例示できると強いです。
- 軽微の例:文言修正、UI微調整、設定値の変更、バグ修正(仕様どおりに直す)
- 追加の例:新規画面追加、新API追加、DB変更、仕様の追加・変更
3) 「バグ」と「仕様変更」を分ける(ここが曖昧だと炎上します)
同じ“直して”でも、意味が違います。
- バグ:仕様・受入基準に違反している(契約内で是正対象になりやすい)
- 仕様変更:仕様そのものが変わる(追加合意・追加見積が自然)
この線引きがないと「それバグですよね?」で押し切られやすいので、雛形で定義しておくと守りやすいです。
コピペ用:変更条項(短文)
- 仕様変更は、チケット起票 → 影響分析 → 追加見積 → 書面(メール等)合意の後に着手する。
- 軽微な修正(__人日以内/__時間以内)は契約内で対応するが、これを超える場合は追加見積の対象とする。
- 仕様・受入基準に適合しない不具合(バグ)は是正対象とし、仕様変更・追加要望は変更手続に従う。
4-4. 保守・運用フェーズの取り決め(現実に守れるSLA)
保守・運用のSLAは、盛ると危険です。
個人のフリーランスだと、無理なSLAはそのまま 契約違反リスクになり得るので、守れる数字に落とす方が安全だと思います。
1) まず「保守の範囲」を決める(ここが曖昧だと無料労働化します)
- 対象:本番障害対応/軽微バグ修正/問い合わせ対応 など
- 対象外:仕様追加、性能改善、UI改修、DB設計変更 など
- 無償期間:納品後○か月(例:1〜3か月)など
- 以降:保守契約(月額) or 都度見積
2) SLAは「初動」と「復旧」を分ける(混ぜると詰みます)
実務では、次の分け方が現実的です。
- 初動(Response):連絡を受けてから着手・状況返信まで
- 復旧(Resolution):実際に直してリリースするまで(依存要因が多い)
たとえば「4時間以内に復旧」は、発注者側の権限やリリース手順に左右されて守れないことがあります。
なので、まずは初動SLAだけ固めるのが安全です。
3) 緊急度分類(Severity)と連絡チャネルを固定する
- Severity定義:Critical / High / Medium / Low(各例も書けると親切です)
- 連絡チャネル:緊急は電話/通常はSlack/記録はチケット など
- 受付時間:平日○時〜○時、休日対応の可否(可なら追加費用)
コピペ用:保守・SLA(例)
- 無償対応:検収完了後__か月間、受入基準に反する不具合(バグ)を無償で是正する(仕様変更は除く)。
- 受付時間:平日__時〜__時(JST)。時間外対応は別途費用とする。
- 初動SLA:Critical=__時間以内、High=__営業日以内、Medium=__営業日以内に一次返信する。
- 連絡:緊急は__(電話等)、通常は__(Slack等)、記録は__(チケット)を正とする。
この章の一言まとめ(雛形の“追加ポイント”は、技術のズレ対策)
エンジニア案件は、契約の文章がきれいでも、
技術要件・品質基準・変更手続・SLAが薄いと、現場で事故になりやすいです。
もし優先順位を付けるなら、まずはこの順で雛形を強くしていただくのが良いと思います。
- 仕様変更の追加合意(4-3)
- 受入基準(4-2)
- 技術要件(4-1)
- 保守SLA(4-4)
5. 業務委託契約書の実務フロー(雛形→締結まで最短ロードマップ)
「業務委託 契約書 雛形」を持っていても、“穴埋め→条件明示→別紙で具体化→締結→運用”まで一気通貫で回せないと、未払い・検収長期化・無限追加・権利トラブルが起きやすくなります。
この章では、エンジニア案件で最短で事故率を下げるための流れを、実務の手順としてまとめます。
※以下は一般的な情報であり、個別案件の法的助言ではありません。
5-0. 最初の30秒で「契約の土台」を固める(ここが曖昧だと全部ブレます)
業務委託契約書(雛形)に取り掛かる前に、まず次の4つだけは先に確定しておくのがおすすめです。
- 誰と契約するか:法人名(登記上)/住所/担当者名(名刺の情報でOK)
- 何を提供するか:成果物(請負)なのか、稼働(準委任)なのか
- いつから始めるか:着手日・期間(終了条件も含める)
- いくら・いつ払うか:報酬の計算方法/支払期日(起算日含む)
ここが曖昧なまま「とりあえず雛形に署名」すると、あとから直しづらい論点(支払い・検収・権利)で詰まりやすいです。
ステップ1:業務委託 契約書 雛形を“案件用”に複製(変数シートでミスを潰す)
まずは雛形を複製し、案件固有の「変数」を先に一枚に集約してから、本文に差し込む運用が安全です。
(本文から直接編集し始めると、条件の抜け・矛盾が起きやすいです…)
変数シート(例:これだけ埋まれば契約は動かせます)
| 変数 | 記入例 | どこに効くか(条項/別紙) |
|---|---|---|
| 契約形態 | 準委任(時間稼働)/ 請負(成果物) | 目的・検収・責任範囲 |
| 業務範囲(やる) | 例:API実装、画面改修、テスト、ドキュメント | 別紙A(スコープ) |
| 除外範囲(やらない) | 例:要件定義、デザイン、インフラ運用、CS対応 | 別紙A(除外) |
| 前提・依存 | 例:API仕様は発注者提供、環境はAWS、アカウント支給 | 別紙A/環境表 |
| 期間・稼働 | 例:2026/1/10〜3/31、月80h上限 | 本文(稼働上限) |
| 報酬方式 | 固定/時給/日当/マイルストーン | 本文(報酬条項) |
| 支払期日 | 例:検収完了日から30日以内 | 本文(支払い) |
| 検収 | 有/無、期限:納品後5営業日 | 本文(検収)/別紙B |
| 知財・二次利用 | 例:著作権譲渡、ただし汎用部分留保・ポートフォリオ許諾 | 本文(知財) |
| 変更手順 | 例:チケット→影響分析→追加見積→書面合意 | 本文(変更) |
| 責任限定 | 例:上限=直近6か月支払総額、間接損除外 | 本文(損害賠償) |
| 連絡チャネル | 例:通常Slack、緊急は電話、議事録はNotion | 別紙(運用ルール) |
実務TIP(事故が減るやり方だけ)
- ファイル命名:
Contract_[案件名]_v1_2026-01-05.docx→ 締結後にPDF化 - レッドライン運用:相手から戻ってきた修正点は赤字・コメントで残す(言った言わない防止)
- 準委任のときは、可能なら 「稼働上限(例:月◯h)」+「超過時の精算(単価・承認手順)」 を入れておくと揉めにくいです
- 請負のときは、可能なら 「受入基準(=検収基準)」+「是正回数/期間」 を先に決めておくと安全です
✅ ステップ2:取引条件の明示(いわゆる3条通知)を“受領して保存する”
フリーランス新法では、発注者が取引条件を、書面または電磁的方法(メール・メッセージ等)で明示することが求められます。
実務では、契約書に含めて兼ねる場合もありますが、トラブルになりやすいのは「着手前に条件が残っていない」ケースなので、受領ログが残る形に寄せるのがおすすめです。
3条通知のチェック(まずは“8項目”を埋める)
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付(成果物/役務)の内容
- 給付を受領する日/役務提供を受ける日(納品日や作業完了日など)
- 受領場所/役務提供場所
- (検査をする場合)検査完了日
- 報酬の額・支払期日
- (現金以外で支払う場合)支払方法に関する事項
ポイントは「口頭だけだと弱い」「着手前に残す」「保存できる形」の3つです。
送付・受領の運用ルール(おすすめ)
- 着手前に受領できない場合は、着手日を後ろ倒し(=納期も自動で順延)
- メール/チャットで受領 → PDF化 or スクショ保存(案件フォルダへ)
- 契約書で兼ねる場合も、最低限「本文の該当条項が埋まっているか」をこの8項目で逆チェックする
3条通知をお願いする一文(コピペ可)
恐れ入ります、着手前の確認として「取引条件の明示(いわゆる3条通知)」をご共有いただけますでしょうか。
業務範囲・検収有無/期限・報酬額・支払期日が確認できる形式(メール/書面/メッセージ等)で問題ありません。
可能でしたら本日中、遅くとも着手前までにご共有をお願いいたします。
【件名つき】3条通知の催促テンプレ(コピペ可)
件名:取引条件の明示(3条通知)ご送付のお願い(〇〇案件)
お世話になっております。〇〇案件の開始にあたり、
フリーランス新法に基づく取引条件の明示(いわゆる3条通知)につき、
電子(メール/メッセージ)で結構ですので、ご送付をお願いできますでしょうか。
受領後に着手いたします。お手数ですがご確認のほどよろしくお願いいたします。
ステップ3:関連書類(別紙)で契約を“具体化”する(本文だけで戦わない)
契約書本体はどうしても抽象になりやすいので、エンジニア案件は 「別紙で具体化」 したほうが、交渉もしやすく、検収も通りやすいです。
まず添付したい“契約パック”(おすすめ順)
- 別紙A:スコープ定義書(含む/含まない/前提・依存)
- 例:「実装対象」「除外」「提供物(仕様書・アカウント・環境)」「責任分界点」
- 別紙B:受入基準(=検収基準)
- 例:「テスト項目」「対応ブラウザ」「パフォーマンス目安」「重大度定義」「みなし検収」
- 別紙C:スケジュール(納期/マイルストーン/レビュー日)
- 例:「スプリント」「デモ日」「検収期限(◯営業日)」
- 別紙D:環境・セキュリティ要件(アクセス/鍵/持ち出し)
- 例:「VPN/MFA」「権限」「ログ」「データ持ち出し禁止範囲」
- 見積書(工数×単価の根拠)
- “追加見積”の基準になるので、後から効きます
ここを入れると強い:順序条項(優先順位)
本文・個別契約・仕様書・見積書が矛盾したときに「どれが勝つか」を先に決めておくと、揉め方が小さくなります。
例)「本契約、個別契約、別紙(仕様書・見積書等)の順に優先する」など。
ステップ4:電子契約で締結(“証拠性”と“保管”までセット)
電子契約の利点は、締結スピードだけでなく、改ざん防止・監査ログ・検索性が高い点にもあります。
また、一般に「紙の契約書(課税文書)」として扱われない形で締結できるため、運用コストが下がりやすいです(ただし、紙で作成・交付する運用に戻すと論点が変わり得ます)。
電子契約でやっておきたいチェック
- 署名者が「契約権限のある人」か(担当者名だけで進めない)
- 締結後のデータ(PDF)と、監査ログ/タイムスタンプの保管場所
- 「紙に印刷して押印し直す」運用を混ぜない(証拠の線がブレます)
保管(フォルダ構成の例)
/Contracts/2026-01_〇〇社_〇〇案件/
00_締結済み/(締結PDF、監査ログ)01_ドラフト/(v1,v2…)02_別紙_見積_仕様/03_検収_請求/(検収書、請求書、入金メモ)
(おまけ)ステップ5:締結後に“お金が入るまで”をワークフロー化する
契約は締結して終わりではなく、検収→請求→入金が回って初めて完了です。
よろしければ、次の3点だけでも仕組みにしておくと、回収漏れがかなり減ります。
- カレンダー登録:検収期限/請求予定日/支払期日(7日前・前日通知)
- みなし検収の運用:期限を過ぎたら、淡々と「検収完了扱いで請求します」と連絡
- 変更ログ:追加依頼は「チケット→見積→合意」の順で記録(口頭で増やさない)
出典・参考
- 公正取引委員会|フリーランス法(特設)
- 公正取引委員会|フリーランス新法パンフレット(取引条件の明示の要点)
- 中小企業庁|フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(改定)
- 国税庁|取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
6. 業務委託契約書の相手別交渉のコツ(業務委託 契約書 雛形を“通す”ための実務)
業務委託契約書(雛形)を「ただの形式」だと捉えてしまうと、交渉はだいたい失敗しやすいです。
実務では、契約書は**“揉めないための運用設計”**であり、あなた(フリーランス)が本来やりたい開発に集中するための土台になります。
特にフリーランス新法では、発注側に取引条件の明示(いわゆる3条通知)が求められ、明示項目は原則7項目+条件付き項目(検査がある場合/現金以外で支払う場合)で最大9項目まで想定されています。
この「明示・記録」があるだけで、交渉の難易度とトラブル率が下がりやすくなります。
(根拠:公取委のパンフ/中小企業庁資料)
6-0. 交渉がラクになる「事前準備」3点(ここを外すと長引きやすいです)
1) “譲れない最小セット”を先に決めておく
全部を完璧にしようとすると、法人相手はほぼ通りません。まずは 最低限の3点だけ決めておくと進めやすいです。
- スコープ:やる/やらない、前提、依存関係(追加は追加見積)
- 検収と支払:検収期限・みなし検収・起算日・支払期日(60日以内の設計)
- 責任範囲:上限(例:直近◯か月の報酬総額)+間接損害除外(可能なら)
2) 交渉は「削除要求」ではなく「代案提示」で進める
相手の心理はだいたいこれです:
「削除=社内稟議が爆発する/代案=最小修正で通せる」
なので、あなたの業務委託契約書の雛形をベースに、代案をセットで出すのが現実的です。
3) “本文が固い会社”には、別紙・覚書・個別契約で逃げ道を作る
大手ほど「基本契約は動かせません」が多いです。
その場合は、個別契約(注文書・SOW)と別紙で運用を上書きできるよう、優先順位(順序条項)で処理するのが王道です。
6-1. 法人相手(BtoB)の業務委託契約書交渉
法人相手は、相手の“契約書雛形”が強いです。ここで消耗しやすい論点はだいたい固定で、特に以下が多い印象です。
- 無制限責任(損害賠償上限なし)
- 成果物・コードの全面帰属(例外なし)
- 無償での無限修正(仕様変更が無料扱い)
- 検収が終わらない(支払が動かない)
6-1-1. BtoBでよくある“不利条項”の見抜き方(赤信号だけ先に拾う)
次の文言があると、実務上かなり危険になりやすいです(見つけたら要注意です)。
- 責任が無制限:「受注者は一切の損害を賠償する」など
- 損害の範囲が広すぎる:逸失利益/特別損害まで含む
- 検収期限がない:合否通知期限がない、みなし検収なし
- 変更手順がない:追加指示が“当然”に吸収される
- 知財が丸ごと:既存資産・汎用コードの留保ができない
- 解除が一方的:発注者都合で即時解除+支払なし、など
6-1-2. 交渉の基本姿勢(通りやすい順番)
「全部直してください」ではなく、通りやすい順に小さく直すのがおすすめです。
- 検収期限(合否連絡期限)+みなし検収
- 支払期日の“計算できる書き方”(起算日+◯日以内)
- 仕様変更=追加見積(手順を型化)
- 責任上限(間接損害除外)
- 知財(最低限:既存資産の留保+ポートフォリオ許諾)
※支払期日の考え方(受領日から60日以内、できる限り短い期間)は公式資料側に明記があります。
6-1-3. そのまま使える「差し替え代案」例(コピペ用の考え方)
※条文の完全なリーガルチェックではなく、交渉の叩き台としての例です。
A) 検収(合否連絡期限)+みなし検収
- 「納品後◯営業日以内に合否連絡」
- 「期限内に連絡がない場合は合格(検収完了)とみなす」
- 「検収完了日を支払起算日にする」
B) 仕様変更の手順(無限修正を止める)
- 「変更要求 → 影響分析 → 追加見積 → 書面(メール可)合意 → 実施」
- “軽微”の定義を数値にする(例:1人日以内/チケット1件など)
C) 責任上限(最小限の防御)
- 上限:例「直近◯か月の支払報酬総額」
- 間接損害・逸失利益は除外
- 故意・重過失は除外、など(会社の方針に合わせて調整)
D) 知財(全面帰属でも“例外”だけ残す)
- 既存資産(受注者が以前から保有しているコード・テンプレ)は受注者に留保
- 成果物は譲渡するが、**ポートフォリオ掲載(匿名化・許可制)**の利用許諾を入れる
- OSS/生成AIの利用条件(ライセンス遵守・台帳化)を合意
6-1-4. 切り出しフレーズ(角が立ちにくい言い方)
- 「トラブル防止の観点で、検収期限と支払起算日だけ整えさせていただけますでしょうか」
- 「仕様変更が起きた際の混乱を避けたく、追加見積の手順を先に型にしておければと思っております」
- 「責任が無制限ですと個人としてリスクが大きく、**上限設定(間接損害除外)**をご相談できれば助かります」
6-1-5. “雛形が動かない会社”への落とし所(現実解)
大手だと「基本契約は変えられない」が普通にあります。ここで粘りすぎると時間だけ溶けます。
おすすめは、基本契約は受けつつ、個別契約(注文書・SOW)や覚書で上書きする形です。
- 個別契約に 検収期限/支払起算日/変更手順だけ入れる
- 優先順位条項で「個別契約・別紙が優先」を入れる
- 3条通知はメールでも成立しうるので、**“証拠が残る形”**を最優先にする
(明示は書面または電磁的方法が前提、という整理は公取委資料に明記があります) - 公正取引委員会:フリーランス法(パンフ)
6-2. 個人相手(toC/個人事業主)の業務委託契約書対応
個人相手は、法人よりも「契約が軽い」分、未払い・仕様ブレ・連絡断が現実に起きやすいです。
なので、業務委託契約書(雛形)は簡略でも良いのですが、代わりに 支払と仕様の確定を強めに設計するのが安全です。
※フリーランス新法の義務が相手にかかるかは、相手が「事業として発注しているか」等で変わり得ます。迷う場合でも、取引条件の明示(メールでOK)を先に出してもらう運用にしておくと揉めにくいです。
6-2-1. 個人相手で“必ず入れたい”3点(ここを外すと事故りやすいです)
- 本人確認(最小限)
- 振込口座名義の一致
- 連絡先(メール+電話など)
- 可能なら身分証の提示(難しければ請求書の宛名・住所の整合だけでも)
- 支払条件(前金・分割)
- 少額:着手金100%前払いでも現実的
- 中額以上:前金30〜50%+納品時残金
- 長期:月次分割(毎月の検収・請求)
※個人は信用枠が弱いことが多いので、「支払サイトを短く」するだけでリスクが大きく下がります。
- 仕様の確定ポイント(どこでFIXするか)
- “仕様確定日”を置く
- 以降の変更は追加見積の対象にする
- 連絡が止まった場合の扱い(例:◯日反応なし→検収扱い、または一時停止)
6-2-2. トラブル防止の交渉例(そのまま言い換えやすい形)
- 「恐れ入ります、個人間の取引ですと入金遅延が怖く、**着手金(前払い)**だけお願いできますでしょうか」
- 「仕様が固まった後の変更は工数が読めなくなるため、FIX後の変更は追加見積で進めさせてください」
- 「連絡手段が途切れると納期が守れなくなるため、**返信期限(例:3営業日)**だけ合意いただけますでしょうか」
6-2-3. “記録を残す”運用ルール(個人相手ほど効きます)
- 合意はチャットだけで完結させず、最後はメールで要約(日時・金額・納期・検収)
- 見積・請求・入金の証跡をフォルダで一元管理
- 仕様変更は「追加見積→OKの返信」まで進めてから着手
6章まとめ:交渉は「自分を守る」より先に「運用を守る」と通りやすいです
業務委託契約書の雛形を軸に交渉するときは、
「私が不安なので」よりも、「運用の確実性(検収・支払・変更管理)を上げたい」という言い方のほうが、法人相手ほど通りやすいことが多いです。
7. 業務委託契約のトラブル予防(契約書で防ぐ)&もし起きたときの対処法
この章では、「業務委託 契約書 雛形」に“追加で入れておくと効く条項”と、万一トラブルが起きたときの「現実的に勝ち筋が立つ動き方」をまとめます。
トラブルの大半は、(1) 支払い、(2) 仕様変更、(3) 権利・利用範囲の3点で起きやすいので、順に押さえていければと思います。
7-1. 未払い対策(契約と運用のセットが必須)
前提(法律の支払ルール:交渉の根拠)
フリーランス新法では、報酬の支払期日は原則として 「給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内」 で定め、定めた支払期日までに支払う必要があります。
また、請求書の提出が遅れた/出ていないことを理由に、支払期日を過ぎる運用は避ける必要があります(発注側の実務注意として明示されています)。
※「受領日」は、検査(検収)がある場合は **検査完了日(検収合格日)**が実務上の起算点になりやすいので、契約書側で「起算日」を固定しておくのが安全です(本文2-3と同じ考え方です)。
未払いを“契約書で”防ぐ:雛形に足すと効く3点
(A) 支払トリガーの固定(起算日をブレさせない)
- 「検収完了日=受領日」
- 「受領日から**◯日以内**(60日以内)」
- 「みなし検収:納品後◯営業日以内に合否連絡がない場合は検収完了」
(B) 分割・前金で“未払いの致命傷”を小さくする
- マイルストーン請求:長期は“納品一括”にせず、区切って請求
- 前金の設定:契約時に30〜50%(個人相手や新規は特に有効)
- 月次払い:準委任(稼働)なら「月末締め」+「翌月末払い(60日以内)」に寄せる
(C) 支払遅延時の“次の一手”を条項で決める
- 遅延利息(年◯%)
- 支払遅延が◯日を超えた場合の 作業停止(中断)
- 中断に伴う納期延長(スケジュール再調整)
- (可能なら)督促費用・弁護士費用の負担整理(※相手の社内規程で難しい場合も多いです)
未払いを“運用で”潰す:請求〜入金のテンプレ運用
未払いは「契約書」だけだと防ぎ切れないこともあるので、運用をワークフロー化しておくのがおすすめです。
- 納品(or 月末):納品物/稼働実績の提出(証跡を残す)
- 検収期限:◯営業日後(カレンダー登録)
- 請求書送付:支払条件に沿って送付(送信ログを残す)
- 入金予定日:支払期日(リマインドを自動化)
- 入金確認:未入金なら即日、丁寧に確認連絡(後述テンプレ)
コピペ用:入金確認(ソフト督促)テンプレ
件名:ご入金状況のご確認(請求書No.__/__案件)
お世話になっております。__です。 __月__日付でお送りしております請求書(No.__)につきまして、 念のためご入金状況をご確認いただけますでしょうか。
行き違いで既にお手続き済みでしたら恐れ入ります。 お支払予定日(__月__日)もあわせてご共有いただけますと助かります。 何卒よろしくお願いいたします。
7-2. 仕様変更への対応(“追加合意”を証拠化して守る)
「ちょっとした修正」の積み上がりは、ほぼ確実に炎上の入口になりやすいです。
これを防ぐには、“追加作業の定義”と“合意フロー”を業務委託契約書の雛形に埋め込むのが一番効きます。
基本の型(証拠が残る順番)
チケット(or 依頼文)合意 → 影響分析 → 追加見積 → 書面(メール・PDF)合意 → 着手
Slack等のチャットだけだと、後でログが流れたり、合意点が曖昧になりやすいので、最後はメール/PDFで合意しておけると安心です。
雛形に入れておきたい“線引き”
- 軽微修正の定義(例:1人日以内/工数◯時間以内/既存仕様の範囲内 など)
- 軽微を超える場合は 追加見積の対象
- 納期・検収基準・報酬の再調整(スコープが動けば三点セットで動く)
コピペ用:仕様変更の追加合意テンプレ(短文) 追加ご要望の件、ありがとうございます。 影響範囲の確認をしたところ、現契約(現見積)の範囲を超える可能性がございます。
①追加内容: ②追加工数見込み: ③追加費用: ④納期影響:
上記でよろしければ、書面(メール返信で結構です)にて追加合意のうえ着手いたします。 ご確認いただけますでしょうか。
7-3. 権利関係の齟齬(「帰属」+「利用範囲」+「NDA整合」を先に固定)
成果物の権利は、納品後に揉めると取り返しが難しい論点です。
業務委託契約書の雛形を作る段階で、「帰属(誰のものか)」だけでなく「利用範囲(どう使えるか)」まで先に文字にしておくことが重要です。
最低限、雛形で先に決めたいこと
- 著作権・知的財産権の帰属
- 譲渡なのか
- 利用許諾なのか
- 一部留保があるのか
- 汎用部分(ライブラリ・ノウハウ)の扱い
- 既存ライブラリ、テンプレート、共通関数、ノウハウなど
- 例:「汎用ライブラリ部分は受注者に留保」と明記し、再利用できる余地を残す
- ポートフォリオ掲載の可否
- 掲載の可否
- 掲載範囲(画面キャプチャ/担当範囲の説明のみ 等)
- 公開時期(リリース後◯か月、事前承諾制など)
- 匿名化条件(社名・サービス名・数値の伏せ方)
- OSS/生成AIの取り扱い
- OSSライセンスの遵守
- 第三者権利侵害を避ける運用
- 機密情報を生成AIへ入力しないことの明確化
- NDA(機密保持)との整合
- 機密情報が含まれる成果物の扱い
- 契約終了後の返却・削除義務
- 再利用・再公開の可否
補足
たとえ自分が書いたコードであっても、
クライアントの機密情報やデータが混ざっている場合、
再利用や公開ができなくなるケースがあります。
そのため、契約書全体(知財条項+NDA条項)で必ず整合を取っておきましょう。
7-4. もしトラブルが起きたときの対処(“順番”が命)
トラブル時は、**感情よりも「証拠」と「手順」**が最優先です。
動き方を間違えると、回収や解決が一気に難しくなります。
実務上は、次の順番で進めるのが現実的です。
① 事実の整理(証拠固め)
まずは、時系列で事実と証拠を整理します。
- 業務委託契約書
- 3条通知(取引条件明示)
- 見積書
- 仕様書・スコープ定義書
- 納品物(提出日時が分かるもの)
- 検収連絡(合否・修正指示・期限)
- 請求書
- チャットログ(Slack等)
※スクリーンショットだけでなく、可能であればログ形式で保存しておくと安心です。
② ソフトに確認(行き違い前提)
最初から強く出ると、相手が防御的になり解決が遠のきがちです。
行き違いの可能性を前提に、丁寧に確認します。
- 先ほどの「入金確認テンプレ」などを使用
- 事実確認に徹し、感情的な表現は避ける
③ 期限を切って正式に依頼(メールで記録)
改善が見られない場合は、メールで正式に依頼します。
- 「いつまでに」
- 「何を」対応してほしいか
- 対応できない場合の代替案(分割払い、日程調整など)
※チャットだけで済ませず、必ず記録に残る形にしましょう。
④ 第三者窓口へ相談(早めに“外”に出す)
一人で抱え込むほど不利になりやすいため、
早めに第三者へ相談することが重要です。
- フリーランス・トラブル110番
- 厚生労働省委託事業
- 第二東京弁護士会運営
- 電話番号:0120-532-110
- 受付時間:平日 9:30〜16:30(※土日祝除く)
未払い・契約トラブルについて、
弁護士による初期的なアドバイスを無料で受けることができます。
また、法令違反の疑いがある場合には、
行政機関への申出が可能である旨も案内されています。
相談窓口の活用(困ったら早めに“外”に出す)
- 未払い・契約トラブルの相談:
フリーランス・トラブル110番(公式)
出典・参考
- 公正取引委員会|フリーランス法 特設サイト
- 政府広報オンライン|フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律(解説)
- フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(改定PDF)
- フリーランス・トラブル110番(公式)
8. そのまま使える業務委託契約書のチェックリスト
契約書の作成や交渉は複雑に感じるかもしれませんが、実は押さえるべきポイントは決まっています。ここでは、実務で即座に使えるチェックリストと、交渉を成功させるための具体的なテクニックをご紹介します。
8-1. 契約前チェック(業務委託契約書 12+α項目)
契約書にサインする前の最終確認は、フリーランスエンジニアとしての自己防衛の最後の砦です。以下のチェックリストを使って、必ず全項目を確認してください。一つでも不明確な点があれば、遠慮なく質問することが大切です。
あなたが確認する要件 基本的な法的要件のチェック
□ 3条通知の8項目が契約書または別紙・メールで網羅されている
フリーランス新法で義務付けられた8項目は、契約の基礎となる重要事項です。契約書本体に含まれていなくても、別紙やメールで明示されていれば問題ありません。
あなたが提示・確認する要件 業務内容に関するチェック
□ 業務範囲/除外範囲が具体的に記載されている
「Webアプリケーション開発」という曖昧な表現ではなく、「ユーザー管理機能(新規登録、ログイン、パスワードリセット)の実装。デザイン作成は含まない」のように、含む機能と含まない機能を明確に区別しているか確認しましょう。
□ 納期(またはスプリント)・検収基準が明確である
納期だけでなく、検収の合否判定期限や、連絡がない場合の「みなし合格」規定の有無も重要です。「納品後5営業日以内に合否を通知。未通知の場合は合格とみなす」といった条項があると安心です。
あなたが提示・確認する支払条件 金銭面のチェック
□ 料金方式・総額が明記されている
時間単価制なのか、固定報酬なのか、マイルストーン払いなのか。それぞれの方式に応じた詳細(上限時間、分割の基準など)も確認が必要です。
□ 支払サイトと支払期日:あなたは「検収完了から30日以内」を基本提案(上限60日)。 検収基準と連動した支払期日が設定され、60日以内という法的要件を満たしているか確認します。「検収完了月の翌月末」のような表現も、60日を超えないか計算してみましょう。
□ 消費税・源泉所得税・振込手数料の負担者:契約段階であなたが明確化。未記載なら原則は支払側負担だが、明記があれば従うため要チェック。 意外と見落としがちですが、これらの負担者が不明確だと、実質的な手取り額が変わってきます。特に振込手数料については、**民法第484条・485条により「契約書に明記がない場合は支払側(クライアント)が負担するのが原則」**です。 一方で、契約書に「受注者負担」と明記されている場合には、例外的にフリーランス側が負担することもあり得ます。 実務では契約書に明記されるケースが多いため、必ず契約段階で確認しておきましょう。 また、源泉徴収の有無は確定申告に直結するため、消費税の取り扱いとあわせて事前に整理しておくことが重要です。
□ **適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)**の扱いが整理されている
インボイス制度への対応状況を確認し、必要に応じて登録番号の記載方法も決めておきましょう。
知的財産権のチェック
□ 知財の帰属・利用範囲が明確である
著作権法27条・28条の権利も含めた譲渡なのか、著作者人格権の不行使特約があるか、ポートフォリオでの利用は可能か、といった点を細かく確認します。
□ OSS/生成AI素材の取り扱いが定められている
オープンソースソフトウェアのライセンス順守や、生成AIで作成したコンテンツの第三者権利への配慮について、事前に合意しておくことが重要です。
リスク管理のチェック
□ **機密保持(NDA)**条項が適切である
目的外利用の禁止はもちろん、契約終了後の情報の返還・削除方法まで具体的に定められているか確認します。
□ **変更・解除(30日前予告の扱いと例外)**が法令に準拠している
フリーランス新法で定められた30日前予告ルールと、その例外事由が適切に反映されているか確認します。
□ 責任の上限設定がある(推奨)
必須ではありませんが、間接損害の除外や、故意・重過失の場合の除外など、リスクを限定する条項があると安心です。
その他の重要事項
□ 準拠法/管轄裁判所が指定されている
紛争時の解決方法が明確になっているか確認します。
□ **順序条項(優先順位)**が明記されている
本契約・個別契約・仕様書・見積書の間で矛盾が生じた場合、どれを優先するかが定められているか確認します。
□ 再委託の可否・条件が明確である
再委託する場合の機密保持義務の伝達や、発注者の承諾要否などが定められているか確認します。
□ 反社排除・コンプライアンス条項がある(あれば尚良し)
企業のコンプライアンス要件として現在は全ての契約書に基本的に反社条項を設定することが求められており、大手企業だけでなく中小企業との契約でも標準的に含まれる条項です。
ワンポイントアドバイス:契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の範囲と期間も、検収基準とセットで一文入れておくと、より安全な契約となります。「検収完了後3か月以内に発見された、仕様書との不適合についてのみ無償で修正する」といった具合です。
8-2. 交渉を成功させるコツ(テンプレート付き)
契約交渉は、対立ではなく「お互いにとって良い条件を見つける共同作業」と考えることが成功の秘訣です。以下、実践的なテクニックをご紹介します。
1) 不利な条項には必ず"代案"を添える
単に「この条項は受け入れられません」と言うだけでは、交渉は前に進みません。代わりに、以下のような建設的な代案を提示しましょう。
- 無制限の損害賠償 → 「直近6か月の支払総額を上限とし、故意・重過失の場合は除外」
- 著作権の全面移転 → 「成果物の著作権は譲渡します。ただし、汎用ライブラリ部分は受注者に留保し、ポートフォリオでの表示は許諾いただけますでしょうか」
- 無償での無限修正 → 「バグ修正は納品後30日間無償で対応します。仕様変更は追加見積とし、軽微な修正(1人日以内の作業)の定義も明確にしましょう」
2) 数字は"相互に"動かす(ギブ&テイクの精神)
一方的な要求ではなく、相互にメリットのある提案を心がけましょう。
- 単価アップを求める代わりに → 納期短縮やレビュー回数削減、支払サイト短縮を提案
- 責任上限の引き上げを求められたら → 総額のアップや保証期間の短縮を逆提案
このように、お互いが納得できるバランスポイントを探ることが重要です。
3) 合意内容は必ず"証拠化"する
口頭での合意は、後で「言った・言わない」のトラブルになりがちです。メールやPDFでの最終確認を必ず残しましょう。チャットだけでのやり取りは、ログが流れてしまう可能性があるため避けることをお勧めします。
また、順序条項を活用して、仕様書と契約条文が矛盾した場合の優先順位を明確にしておくことも重要です。
交渉メールの例文(そのままコピペして使えます)
件名:契約条件の一部調整のお願い(責任限定/検収基準)
〇〇株式会社 〇〇様
お世話になっております。
契約条件について、以下2点のみ調整をご提案させていただきたく、ご連絡いたしました。
1) 損害賠償の上限設定
直近6か月の支払総額を上限とさせていただき、故意・重過失の場合は除外とする
2) 検収基準の明確化
納品後5営業日以内に合否のご連絡がない場合は、検収合格とみなす
いずれも、プロジェクト運用の確実性向上と、リスク分担の明確化を目的としたものです。
貴社にとってもメリットのある内容かと存じますが、ご確認のうえ、可否をご教示いただけますでしょうか。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
8-3. 契約後の管理ポイント(運用まで面倒見切る)
契約締結がゴールではありません。むしろ、契約後の適切な管理こそが、トラブルを防ぎ、円滑なプロジェクト遂行を実現する鍵となります。
書類の一元管理(電子帳簿保存法も意識して)
契約関連書類は、後から参照することが多いため、体系的な管理が不可欠です。原本(締結済みPDF)、見積書、仕様書、検収書、請求書を同一フォルダでバージョン管理することをお勧めします。
フォルダ構成の例:
/Contracts/2025-08_〇〇社/
├── 2025-08-22_基本契約_v1.pdf
├── 2025-08-22_見積書.pdf
├── 2025-08-22_仕様書_v1.pdf
└── 請求書/
ファイル名には検索要件(日付・相手先・金額)を満たす情報を含め、後から探しやすい命名規則を決めておきましょう。エクセルなどで管理台帳を作成しておくと、さらに便利です。
支払期日の自動リマインド設定
カレンダーアプリを活用して、検収期限・請求日・支払期日を登録し、7日前と前日に通知が来るよう設定しておきます。これにより、重要な期日を見逃すリスクを大幅に減らせます。
支払いが期日を超過した場合のリマインドメールのテンプレート:
お世話になっております。
○月○日付でお送りした請求書(No.□□□)について、
ご入金状況をご確認いただけますと幸いです。
行き違いでご入金済みの場合は、ご容赦ください。
更新・終了の"30日前通知"の準備
長期契約の場合、更新や終了の意思表示を30日前に行う必要があります。通知文書のドラフトを事前に用意しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
通知文書の例:
本契約は〇年〇月〇日をもって満了となりますが、
引き続き契約の更新を希望いたします/契約終了の意思表示をいたします。
つきましては、必要な手続きについてご教示ください。
プロジェクト終了時のクローズ作業
プロジェクトが終了したら、以下の作業を確実に行います:
- アクセス権の棚卸しと削除:リポジトリ、クラウドサービス、VPNなど、全てのアクセス権限を確認し、不要なものは削除
- 返却物・データ削除の証跡を残す:機密情報の削除完了報告書を作成し、提出
- 最終的な成果物の引き渡し確認:ソースコード、ドキュメント、その他の成果物が全て引き渡されたことを文書で確認
インシデント対応の線引き
保守フェーズでは、以下の分類と対応時間を明確にしておきます:
- バグ対応:契約で定めた無償対応期間内かどうか
- 仕様変更:追加見積もりが必要な案件として扱う
- 緊急対応:SLA(サービスレベルアグリーメント)に基づく初動時間
- Critical:4時間以内
- High:1営業日以内
- Medium:3営業日以内 注意:これらの対応時間は一般的な企業体制を想定した例です。フリーランス個人の場合は、実際の稼働体制(平日昼間のみ、休日対応の可否等)を考慮して現実的な時間設定に調整することが重要です。無理な設定は契約違反リスクを高めるため、事前に十分検討しましょう。 連絡チャネルも、緊急度に応じて使い分けることが重要です(緊急時は電話、通常はメールなど)。
実務メモ:**検収→請求→支払い(60日以内)**の3点セットは、ワークフロー化しておくと漏れが防げます。タスク管理ツールやプロジェクト管理ツールを活用して、各フェーズの完了を確実に管理しましょう。
これらのチェックリストと管理手法を活用することで、契約に関する不安を解消し、本来の開発業務に集中できる環境を整えることができます。最初は手間に感じるかもしれませんが、一度仕組み化してしまえば、その後の案件でも同じプロセスを適用できるため、長期的には大きな時間の節約につながります。 契約管理は、フリーランスエンジニアとしてのプロフェッショナリズムを示す重要な要素でもあります。きちんとした管理体制を持っていることで、クライアントからの信頼も高まり、より良い条件での案件獲得にもつながるでしょう。
9. コピペ用:業務委託契約書のミニ雛形(抜粋)
実際に使える契約書の雛形を、書き換えやすい形で提供します。これは最小限の要素だけを含む"芯"の部分ですので、案件に応じて肉付けしてください。なお、3条通知の8項目は必ず事前にメール等で送付することを忘れないでください。
# 業務委託基本契約(ミニ版|2025対応・3条通知兼用)
**発注者**:____(名称・住所)
**受注者**:____(氏名/名称・住所)
**業務委託をした日**:__年__月__日(※3条通知(1)(2))
**契約開始日**:__年__月__日
---
## ◆ 3条通知(取引条件の明示)※本契約書は以下の8項目の明示を兼ねます
1. **発注事業者・フリーランスの名称**:上記記載のとおり
2. **業務委託をした日**:上記記載のとおり
3. **給付(役務)の内容**:第1条参照
4. **給付を受領する期日/役務の提供を受ける期日**:第1条・第3条参照
5. **給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所**:第1条参照
6. **検査完了期日(検査がある場合)**:第3条参照
7. **報酬の額および支払期日**:第2条参照
8. **報酬の支払方法(現金以外で支払う場合のみ)**:第2条参照
> 電子的な方法で本契約を明示・締結した場合であっても、受注者から**書面交付の求め**があれば、発注者は遅滞なく書面を交付する。
---
## 第1条(業務内容・場所・提供期日)
受注者は、**別紙A(仕様・スコープ)**に基づき、__の開発・改修業務(以下「本業務」)を行う。
1. **業務内容**:別紙Aに詳述(**含む事項/含まない事項**を明示)。
2. **役務の提供期日**:__年__月__日(またはスプリントごとの期日表による)。
3. **提供場所**:リモート/__(所在地)/その他:__。
4. **作業環境・前提**:VPN/MFA 必須 等。
> 範囲外(例):インフラ運用、CS対応、____ など。必要に応じて別紙で明確化。
## 第2条(報酬・支払)
1. **報酬**:__円(または**時間単価**__円、月額__円、上限__時間/月 等)。
2. **支払期日**:**給付受領日(=第3条の検収合格日)から__日以内**とし、**60日以内**の範囲で具体日を定める。
3. **支払方法**:銀行振込(__銀行__支店/口座__)。
- 現金**以外**で支払う場合の方法・要件:__(例:振込/送金サービス 等)。
4. **遅延利息**:年__%。手数料負担:__側。
## 第3条(検査・検収)
1. 受注者は成果物を納品し、発注者は**__営業日以内**に合否を通知する。
2. 不合格の場合、受注者は合理的期間内に是正し、再検査を行う。
3. **検査完了期日**:__年__月__日(スケジュール表がある場合はその期日)。
4. 期限までに合否の通知がない場合は**合格(検収完了)とみなす**。
この**検収完了日を請求起算日とする**。
## 第4条(知的財産)
1. 成果物の**権利帰属**:__(例:発注者に帰属。受注者はポートフォリオ用途の表示許諾あり)。
2. **著作権の譲渡**を行うときは、**著作権法27条・28条**の権利を含めて譲渡し、**著作者人格権不行使**の範囲を定める。
3. **OSS/生成AI**の利用はライセンス遵守・出典管理を行う。
## 第5条(秘密保持)
目的外利用・第三者提供を禁止し、終了時は返還・削除する。再委託先にも同等の義務を課す。
## 第6条(変更手続)
仕様変更は、**チケット合意 → 影響分析・追加見積 → 書面(メール)合意 → 実装**の順で行う。軽微修正(1人日以内 等)の定義は別紙で定める。
## 第7条(契約期間・解除)
1. 期間:__年__月__日から__年__月__日まで。
2. 双方は、やむを得ない事由を除き、**30日前予告**により解除/不更新ができる(法定の例外事由がある場合を除く)。
## 第8条(責任の範囲)※推奨の防御条項
1. 当事者の**故意または重過失**による損害を除き、責任上限は**直近6か月の支払総額**とする。
2. **逸失利益・間接損**は除外する。
## 第9条(準拠法・管轄)
日本法を準拠法とし、__地方裁判所を**専属的合意管轄**とする。
---
### 【任意付記】再委託に関する明示(該当する場合のみ)
- 本件が**再委託**である旨:はい/いいえ
- **元委託者の名称**:__
- **元の支払期日**:__年__月__日
> 上記は3条通知の**条件付き追加明示**に対応(該当時のみ追記)。
業務委託契約書の雛形の使い方(カスタムの観点)
この雛形は、あくまでも出発点として活用してください。実際の案件では、以下のような点を追加・修正することが必要になるでしょう。
プロジェクトの特性に応じた追加条項
- アジャイル開発の場合:スプリントの定義、バックログ管理の方法
- 保守案件の場合:SLA、対応時間、エスカレーションルール
- 機密性の高い案件:より詳細なNDA条項、監査への協力義務
技術的な要件の明記
- 使用言語、フレームワーク、ライブラリのバージョン
- 開発環境、テスト環境、本番環境の仕様
- コーディング規約、ドキュメント作成基準
コミュニケーションルールの設定
- 定例会議の頻度と形式
- 進捗報告の方法とタイミング
- 緊急時の連絡体制
この雛形をベースに、クライアントとの対話を通じて、お互いにとって最適な契約書を作り上げていくことが重要です。
まとめ:業務委託契約書の雛形は自分を守る最強の武器
ここまで、フリーランスエンジニアが知っておくべき契約書の作成方法と、フリーランス新法への対応について詳しく解説してきました。
契約書の作成は面倒に感じるかもしれません。しかし、これは自分の時間、スキル、そして生活を守るための最も重要な投資です。最初は時間がかかるかもしれませんが、一度しっかりとした雛形を作っておけば、その後の案件では効率的に契約を進めることができます。
特に重要なのは、3条通知の項目を必ず事前に明示すること、支払期日を60日以内に設定すること、そして自分のリスクを適切にコントロールする条項を盛り込むことです。
フリーランスという働き方は、自由度が高い反面、自分で自分を守る必要があります。契約書はそのための最強の武器となるのです。
次の一歩:業務委託契約書の不安を"実務で"解消しよう
フリーランスとして安心して開発に集中するためには、契約面での不安を解消することが不可欠です。しかし、一人で全てを対応するのは大変ですよね。
そんなあなたのために、実務の伴走と案件選定・交渉支援を提供するサービスがあります。
Track Works は、エンジニア向けに以下のサポートを提供しています(求職者の費用は無料):Track Works(トラックワークス)|副業・フリーランス×高単価AI案件|先端技術でキャリアと収入UP)
提供サービス(業務委託契約書の実務サポート)
1on1メンタリング/キャリア相談
経験豊富なメンターが、あなたのキャリアプランに合わせたアドバイスを提供します。技術的な相談から、フリーランスとしての生き方まで、幅広くサポートします。
契約・請求・稼働調整などの実務サポート
契約書のチェックから請求書の作成、稼働時間の調整まで、フリーランスの実務をトータルでサポートします。
※ただし、法的助言は対象外となります
あなたの希望に沿った案件提案・単価交渉の支援
市場価値に見合った適正な単価での案件を提案し、交渉もサポートします。「自分で単価交渉するのは苦手」という方も安心です。
週2–3日/副業/フルリモートなど柔軟な働き方の提案
ライフスタイルに合わせた働き方を実現できる案件を厳選して提案します。家族との時間を大切にしながら、キャリアアップも実現できます。
フリーランスエンジニアとして、契約面での不安なく、本来の開発業務に集中したい方は、ぜひ一度相談してみてください。
👉 今すぐ相談する:Track Works(トラックワークス)|副業・フリーランス×高単価AI案件|先端技術でキャリアと収入UP) 契約書の知識を身につけ、適切なサポートを受けることで、フリーランスエンジニアとしてのキャリアをより充実したものにしていきましょう。あなたの成功を心から応援しています!